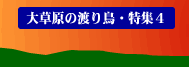|
<はじめに>
小林旭さんが『大草原の渡り鳥』の撮影中に、ご自分で書かれた随筆をお届けします。 これが書かれたのは、昭和35年の夏、渡り鳥・流れ者シリーズで人気が大爆発している
真っ最中であり殺人的スケジュールの中で書かれた貴重な文章でもあり、渡り鳥シリーズ、流れ者シリーズのロケ話がつづられています。その規模の大きさや、地元ファンの歓待ぶりなど、当時の熱狂的な騒動を想像してください。
(※青文字部分は管理人コメント)
渡り鳥随筆
この一年余りの間に、「南国土佐を後にして」以来、既に十本目の渡り鳥シリーズに出演したことになる。
いま、その十本目の作品「大草原の渡り鳥」の撮影で、さいはての秘境、北海道の阿寒に来ている。赤い夕陽に映える荒漠とした原野のたたずまいは、いつしかボクを西部劇の主人公になったかのような錯覚に陥れるのだ。
『十本目の作品「大草原の渡り鳥」』とある。渡り鳥シリーズは厳密にいうと、本作は「南国土佐を後にして」を入れても6本目となるはず。
「ギターを持った渡り鳥」「口笛が流れる港町」「渡り鳥いつまた帰る」「赤い夕陽の渡り鳥」の次となる。つまり、ここでは流れ者シリーズをも含めたものと考えられます。しかし、これまでは「海から来た流れ者」「海を渡る波止場の風」「南海の狼火」の3本が撮られているだけ、単なる勘違いだとも思えない。
そこで、類型作品を探すと「波止場の無法者」(1959年11月公開)共演:浅丘ルリ子、小沢昭一…がある。これは、渡辺武信先生もシリーズの一つとして捉える
ことができると述べられています。これを含めることにより、10本目の作品となる。
「南国土佐を後にして」の監督は初めは舛田利雄監督が予定されていた。しかし、同監督は「歌謡映画では……」と渋ったとか。そのため斉藤監督に、おハチがまわってきた。が、斉藤監督はアクションが不得手だった。しかし、それまでの氏の作品の興行成績がよくなかったので、気晴らしにやってみようという気になったとか。これが意外にヒットした。
一年前前のことだった。山崎撮影所長から、「南国土佐…」の出演決定の報せを受け、所長室で、ペギー葉山さんと顔を合わせた。当時全国を風靡していた彼女の歌は、ボクも大変好きなものだった。
今でこそ、ボクもおけさ節、ダンチョネ節、など民謡くずしの歌を吹き込んではいるが、その頃はあこがれの歌であった。
渡り鳥シリーズの歴史は、今更ボクが喋々するまでもないことだ。だが、その誕生の秘話は余り知られていない。日活はお家芸の単にタイムリーな歌謡ものにするか、あるいは、これを大作に仕立てるかの二者撰一に立たされた当時の話である。この時、江森常務の大英断がなかったら、恐らく一篇のヒット作に止まっていただろう。
江森常務の決断こそ、いまこそスクリーンに息づく滝伸次の誕生を可能にしたのだ。
「南国土佐を後にして」、この待望の台本が完成し、一気に読み通したボクは、感動したものであった。 これは、活劇王国日活でさえも今まで試みたこともなかった途方もなく痛快な、見事に常識をうち破った活劇のヌーベル・バーグであった。“無国籍映画”などという非難は、この面白さに較べたら微々たる問題だった。
これを成功させることによって、日活に新しい一つの方向が完成するのだ、と、斉藤武市監督とともにボクを励ましてくれた常務の言葉が今もって忘れられない。
南国高知はボクたちロケ隊を歓迎してくれた。これはまさしく天の加護のように感じられた。何故ならボクに多少の不安があったからだった。 ボクにこんな責任ある大役が出来るだろうか、失笑を買う不出来では、金輪際この日活新方式の活劇が断たれるという不安であった。(中略)
娯楽こそ映画の真髄である。ボクの映画観がすっきりと割り切れる思いがした。「大衆、特に若い人は英雄的な人物が好きだ…社会に閉ざされた夢をこの英雄に求める」
この明快な社会心理学が渡り鳥滝伸次を生み、流れ者野村浩治を生み、銀座旋風児二階堂拓也を生んだことをボクはよく知っている。それだけに勧善懲悪の英雄は強くなければならなかった。
ボクはそのためにボディビルや、体操などで身体を鍛えた。無論好きな酒も断った。その上、早射ちの拳銃さばきの練習で、指に血の出るのも忘れた。これはボクの苦労だけではなかった。殺し屋錠(宍戸)さんを始め、
みんなの努力によって日本版西部劇の完成をいそいだのである。いずれにせよ、活劇王国日活にあって初めて成しうる冒険であったし、成功でもあったのだろう。そして、その成功はボクの生涯のよろこびであろう。
「南国土佐…」は、まさに日活映画の新たな社運を賭けた企画であったともいえよう。それまでの日活の歌謡映画は、本数にして20本余り(「夜霧の第二国道」「あん時ゃどしゃぶり」「東京のバスガール」「西銀座駅前」「船方さんよ」「未練の波止場」「赤いランプの終列車」他)、全てが白黒映画である。しかし、「南国土佐…」は異例のカラー映画であることから、その意気込みが感じられる。『嵐を呼ぶ男』以後の大ヒットに恵まれない状況が続いていた日活映画にとっては、石原裕次郎さんに続くスターづくりが急務だった。
役作りのためのアキラさんの真摯な努力は、後の全ての生き方に通じるものがあったのではないだろうか。
渡り鳥伸次の誕生は昨年の九月、「ギターを持った渡り鳥」であった。その伸次が活躍した舞台は北海道函館全域が選ばれた。
当時の新聞は、滝伸次の登場に面食らったかのようだった。しかし、どの新聞も一斉にこの臆面もなく大胆に西部劇の手法をとりいれたこの作品に、 戸惑いながらも期待を寄せてくたれた。
毎日新聞はこう書いた。
「斉藤監督はこの映画で西部劇のクライマックス・シーンをいくつか借用しようとたくらんでいる。例えば映画のファースト・シーンで、殺し屋の宍戸錠の対決場面などは『ベラクルス』そっくり、……しかし、函館は斉藤監督が『白い悪魔』以来すっかり惚れ込んだ土地、この映画のように、西部劇調ものを撮影するには絶好の地形を備えている」
ボクはこの記事から、非難よりも期待の多いことを逆説的にくみとったものだ。
北海道の荒漠とした広さの中に、ギターをかかえ、馬にのり、あてもなく渡り歩き、悪を倒して行く西部男のロンリーマン、滝伸次の異様なスタイルは人目を惹いた。そして、函館山での危険な撮影の毎日は、つめかけたファンの度肝を抜いた。ボクはどこも傷だらけとなったが、役者冥利につきる新しい任務に少しも悔いはなかった。(中略)
当時の映画人気は、アメリカ西部劇の人気も一段落し、渡り鳥シリーズの登場は若い人たちを中心に熱狂的に迎え入れられ、シリーズを追うごとにその数は増える一方となった。巷には主題歌や挿入歌が流れた。
第二作目が「口笛が流れる港町」であった。そのロケ地は、函館から遠く日本の最南端九州宮崎県の海老野高原であった。
ここは霧島火山帯に属する高原で、至る所岩間から硫黄が噴出し、息苦しくなるくらいの土地だ。映画のロケ隊が入りこんだのは、 はじめてという処女地でもあった。この時のボクのいでたちは、袖ポケットにピストルという全くの西部劇スタイルで、これにウェスタン調の主題歌をうたうといった趣向だった。
いよいよ快調な演出をつづける斉藤監督も「映画の中でのリアルさをすっぱり捨てて、娯楽としての映画の徹底した面白さをねらう」と、張り切っていた。
海老野高原を撮り終えたボクたちは宮崎市に入り、お祭りシーンを撮影、ここでも大変な歓迎をうけたものだった。
“渡り鳥”と“流れ者”のちがい
日本版西部劇の第三作は、新しいシリーズとして流れ者野村浩次の初登場「海から来た流れ者」であった。これを担当する山崎徳治郎監督は、事件記者シリーズでそのスピードある演出が
高く評価されていた。ある日、山崎監督はボクに、伸次と浩次の違いをこう説明してくれた。
「この流れ者の主人公は、渡り鳥と違って、ロケ現場となる土地に行くのに、完全なる理由がある。これに反して伸次はあてもない旅を続ける」
たしかに「海から来た流れ者」の主人公は、何者かに殴打され、やがて、意識を取り戻した時に、そばにあった大島行きの切符に気づいて、大島にのりこむという目的があった。
だから、当然、話の展開が、渡り鳥とは違っていたし、ボクのいでたちも西部劇調のものから、スカッとした背広姿で登場することになった。ただ、地方色を活かし、民謡を採り入れ、
大自然を背景にしたスケールの大きさの点では、共通していたし、痛快な娯楽性をねらう趣向も同じであった。
黒潮と御神火の大島ロケは、ボクをはじめ、ルリ(浅丘)ちゃん、ター坊(川地)、良(葉山)さん、錠さんらスタッフ・キャストの総勢154名。まさに島全体が、日活一色にぬりつぶされた感じだった。
有名な三原山噴火口をはじめ、大砂漠、溶岩の断崖など、火山島のダイナミックな景観をあます所なく撮りまくった。 なかでも撮影に一番苦労したのは、錠さんとの噴火口際の格闘シーン。とにかく、ゴツゴツした溶岩の山道を重い機械を運び上げるのに半日もかかり、その上、
火口ぎりぎりの断崖のロケ現場は、一般人はもちろん立入禁止の場所、眼下の大火口からは、無気味な噴煙が吹き上げ、溶岩のすき間からも水蒸気(ガス)が噴出していて呼吸困難にまいるスタッフも
続出する有様であった。しかし、風の具合で噴煙がまともにロケ隊にぶつかると、その危険をおかした撮影だけに、そのシーンはものすごく迫力を増した。
ボクだけが足場の悪い溶岩の上を飛び回りゴキゲンなのに、スタッフは肝を冷やしていた。一方、溶岩の上をひきずり廻されたルリちゃんなどは、スカートはズタズタ、脚も血だらけという有様で、
いつもの茶目っ気ぶりは姿を消した。
この大島ロケ以上の危険撮影を冒したのが、流れ者シリーズの第二作「海を渡る波止場の風」の桜島噴火口ロケだった。九州最南端の桜島といえばぶっそうな活火山だけに、人っ子ひとり見あたらず、桜島名産のビワの
荷車が通るだけの殺風景さである。「こんなロケは初めてだ。ファンがいないと撮影の気分が出ない」と歓迎攻めになれたスタッフがグチるほど。桜島を終えたロケ隊は、指宿温泉に向かった。ここでは丁度、島津夫妻の新婚旅行と重なり、西南戦役以来の人出といわれ
たほどの人出で、この整理に警察の機動部隊まで出動した。 (中略)
去る八月、一年ぶりに四国愛媛の宇和島に飛んだ。このシリーズ第三作目「南海の狼火」のロケだ。
名物の闘牛や、真珠の養殖所を背景に、野村浩次の活躍を描いた。紅白の天幕を張りめぐらした和霊神社の境内に、、再び四国は、おなじみのおけさかぞえ歌。
“海は荒海 向こうは佐渡よ”と唄われるように、ロケ隊をのせた連絡船はおおゆれで、ルリちゃんをはじめ、早苗ちゃん、マリちゃんなどの女性群は、さすがに降参、ボク一人がユウユウせまらず、タフガイぶりをみせて女性達にうらやましがられたものだ。佐渡では大変な歓迎を受け、おけさ踊りの撮影になんと五千人余名が参加しての未曾有の撮影だった。撮影前、おけさ踊りを覚えようと、研究会に入ったルリちゃんの踊り姿は、鳥追笠に千鳥、ファンから「可愛い、可愛い」の嬌声を浴びていた。
そして渡り鳥シリーズ第四作目は“佐渡おけさ”を後にして、福島の会津磐梯山に向かった。「赤い夕陽の渡り鳥」。
この頃にもなると、ボクの乗馬ぶりも板につき、手綱さばきも騎手並で不毛地帯で知られた、ここスカイ・ライン・コースをギター片手に駆けのぼれば、観光バスの窓から女学生の嬌声が盛んにとんだものだ。
猪苗代湖、五色沼など、福島名所をロケし、抒情アクションの真髄をついた感じ“会津磐梯山は宝の山よ……”民謡とアクションは、ここに渾然と一体なり、渡り鳥シリーズの人気は、いま最高潮とか。
(資料:「別冊近代映画・大草原の渡り鳥特集」より)
特集1 ロケ便り へ
特集2 名コンビ対談 へ
特集3 監督インタビュウ へ
|