「お世話になったあの人へ」
2002/11/30
男の中には同時に女の因子があってこれがフィクションの生まれる理由だ。
フィクションだらかこそあらゆる類推が可能だ。
旭の歌に涙が出る理由の一つはこれだと思う。
軽いテンポで終始するこの曲は、 「こんな女がいたら可愛いなと思う男の幻想」の産物かも知れない。
性差が混沌とした今では歌われることがないのも無理はないが 、かつては、こんな男の幻想に女も添うように生きていた時代が確かにあった。 男のエゴイズムといわれようと、現今の「女を物のように扱う」オタク感覚とは全く異なる。
確かに女は不幸でなければならないが、その不幸の原因は男である自分でその後ろめたさを、彼女に解ってもらいたいという不可能に近い構造があるからこそ実の女に対しても相応のわきまえがあったはずである。
「遊んでくれてありがとう、でもわたしは言わなかったけど本気だったのよ」
ほんとの女がこんなことを言うわけはない、だから女性が歌うと全く真実味がない。 ところが旭が歌うとこの幻想の女が輝き出すのだ。コミック風にカリカチュアライズされた歌詞ゆえに 軽快に3番まで来て「命の恋でした」の一行は、さらっと歌われるほどインパクトがある。
「命の恋」をここにもってきた中山大三郎はすごい。言葉が生きていることを証明するのが詩人だが、 さらにこのフレーズを絶対に陳腐にしないのが旭の声だ。 ほとんどの演歌が「女たらし」のような歌手によって歌われている中、旭の演歌は大げさではなく「救い」だ。
歌詞は他人から与えられた物だから、内容や表現に多少の誤解が生じるのは仕方ない。
でも、旭の声は、ときに悲しく美しい、優しい男の泣き声のように聞こえる。
清い演歌というのも可笑しなものだが、こんな純な声の歌手が他にいるだろうか? 耳が単なる集音装置だったと気付かせてくれたのが旭の声だ。
歌の上手い歌手はいる、綺麗な声の歌手もいる、歌心、癒しとやらを持った歌手もいる。どれも確かに耳をくすぐるが、そんなレベルを超えハートを直撃する声が旭の歌い方にはある。
あんな声で「やくざの詩」を歌える歌手がほかにいるだろうか。
はたちそこそこで歌った歌を60になってから歌って失笑を買わない歌手が他にいるだろうか?
「お世話になったあの人へ」
言葉少ない控えめな青年のような旭の声だからこそ、この歌は凡百の夜の酒場歌を越えている。
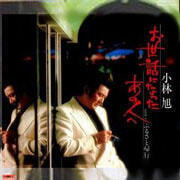
「銀座旋風児」
2002/12/01
「俺が嫌だといったって、誰かが俺を喚びに来る」
1959年、ほぼ旭初期の代表曲にこんなフレーズがあったなんて眼を疑った。
なぜなら私が長年小林旭という男に抱いていたイメージがまさにこれだったのだ。
それに間違いのなかったことは自伝「さすらい」で彼の人生を垣間見た時納得したものだ。
作詞家はまだ若僧の彼に既に旭そのもののキャラクターを視抜いていたのだろうか。
「俺が嫌だといったって」
嫌だけど、嫌とは言わない、いわんや旨いとか不味いとか言わない。
「出されたものを黙って食う」
それが呼びに来た者に対する旭の返事だ。
私が旭を好きな理由は彼の歌声からこういう男のストイシズムを感じるからだ。
「旨くても食わない」のではない。手を付けるべきか付けざるべきかの判断を己がしないということである。それは自分が決めるんじゃなく、呼びに来た誰かでなければならない。
その「誰か」も具体的に言わず「風が呼んでる」と表現する所がなんとも旭らしく、ニクイところだ。
こう書くとまるで主体性のない人格のようだがそうではない 「今日も嵐の中に立つ」男に主体性がないなどとは言わせない。
そうでしょ?
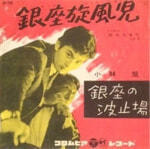
「オロロン慕情」
2002/12/02
聴きながらいつも考えるのだが、「男にだまされ」のこの男というのは、ひょっとして「俺」つまり自分じゃないかと。
網走はどっちかというと健さんの舞台だが旭もよく似合う。
投獄の時に見送りに来た娘が出獄時には死んでしまっていたというようなイメージにしたい。
3番とも「俺と」で始まるから自分が服役中に他の男と知り合うような女じゃないようだし、この女の苦労というのはどうも自分が蒔いた種に原因があると考えた方がしっくり来る様な気がする。
そうだよと遠藤実が言うかどうかわからないが、はじめのうちはずっと自分以外の男にだまされて死んだんだと解釈していた。
皆さんはどうですか?
でも旭が娘の死を人のせいにするとはどうにも考えられないだろう。
もちろん「だまされ」と歌うが、これは騙すつもりじゃなくても結果的に「騙すことに」なってしまった自分への自虐的な表現と解釈したい。
この方が取り返しの無さがより強調されるから。
それにしても現代というのは「世の中には取り返しのつかない」ことがあるのだという感覚になんと鈍くなっていることよ。
鳥にくわしい知り合いがいつか言っていた「いろんな鳥の声を聴いたがカモメがいちばん悲しい声で鳴く」と。
この曲には時を経ていくつかのバージョンがあるようだが、私は 「オロロンバイ」のフレーズをノンバイブレーションで歌う、初期の録音の方が 好きである。もちろん他のだって大好きなんだけどね。
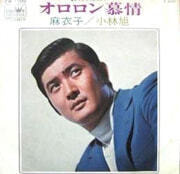
2002/12/02
この歌のこのパートになんでこういう表現が出てくるのかどうしても解らなかった。 何年か前に「シックスセンス」という映画があって、主人公は実は死んでいるという オチのあるストーリーだが、それではたと気が付いた。
その時は唖然として、それこそ「俺は生まれつき馬鹿」なんじゃないかと思ったくらいだ。
でも「ごめんね」と歌っているこの男が幽霊(あんまり適切な表現じゃないが)だと仮定すれば
「嘘が言えず遠回り」が見えてくる。
「嘘が言えず」なんて変だなあ嘘が言えないなら立派なもんじゃないかと、普通は思う。
実は本当の事を言っちゃったのである。愛し合っている男女において本当のことを言ってはまずい状況とはどんなシチュエーションか?
「お前のことは死んでも忘れない」と死ぬ前に言ってしまった場合である。
これでは女は心の傷が癒えるまで相当遠回りするはずだ。
だから、俺が「嘘が言えずに、遠回りして」というよりもお前が「遠回りして苦労かけるね」と次のフレーズにくっつけるとわかりやすいかも。
「命を賭けているのに、花が咲かない」という表現もなんとなく腑に落ちる。
3番なんかまさに「シックスセンス」のワンシーンだと思いませんか?
いつも思っている女にわざとつれなく心にもないことを言わせざるを得ない旭がこの時ばかりはうっかりほんとのことを言ってしまった。
だから「本当にごめんね」のくどさに切実感が漂うのだ。
もちろん旭が死んでは困るがそう思わせるスピリットが彼にはある。
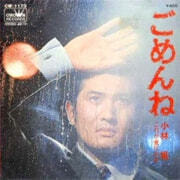
2002/12/03
おやじに殴られたこともない。
祭だって好きじゃなかった。
でもこの歌を歌うと泣けるのは何故だろう。
「旭の声がいいからだよ」というのは、まあおいといて。
歌詞は必ずしもその人の実人生に添うものでなくともいいのだ。
また個人的に感情移入できるからといって泣けるものでもない。
それを狙ったあざとい歌詞回しもあるからだ。
手前味噌になるかもしれないがその理由は歌詞にあるんじゃなく、
その歌詞を勝手に解釈する自分のイマジネーション(想像力)、
あるいはファンタジー(夢遊力)にあると思うのだ。
言葉というものはその人の意識でいかようにも解釈出来るし、していけないと言うこともない。
「いい女」と書いてあればその女がどんな女かは十人とも違う。
だから詩をを読んで泣けるというのはその人の能力と考えていい。
もちろんこんな能力があるからといって偉いとか偉くないとかではない。
能力というものは使い方次第でマイナス方向に作用することもある。
泳げるか泳げないかという程度のものだ。泳げたために溺れたということもある。
ところがこのイマジネーション、現代のように作為的なヴィジュアルばかり見せられると確実に低下する。
逆に上昇するのがイリュージョン(妄想力)、これはいけない。
そこで皆さんの好きな「人生は咲きながら散る桜」のフレーズ。
私個人のイマジネーションとしては「桜は散りながら咲く」ものだと思うがどうか?
作詞家としては音声として歌われるので「咲く、桜」と書くと「さく」がダブって綺麗じゃないと考えたのかもしれない。
しかし自分はいつも「散りながら咲く、桜」と心の中で歌っている。
もちろんこのほうが旭らしいからである。ちょっとヤクザっぽすぎるが咲きながら散っちゃあかっこわるいでしょ。

「にっぽん無宿」「ダイナマイトが百五十屯」
2002/12/03
「さんざ遊んだむなしさは 他人にゃとうてい判るまい」
このフレーズに共感出来る人はいる。が実感できる人は多くはないと思う。だからこんな境地に達することのない極道は多分偽物である。
一般的には満足するまで目一杯遊ぶという健全コースをたどる私たち。
しかし、遊び尽くした果てのむなしさとは一体いかようのものだろう。
「とうてい判るまい」とは、理解して欲しいなどという甘えを越えて
もはや説明不可能ということだから、これは「遊び人」というより修行僧「行」に近い境地だ。飲む打つ買うもここまで行けば求道めいてくる。
「他人にゃとうてい判るまい」はともかく「さんざ遊んだむなしさ」という虚無感はやはり旭のものであって優等生的な裕ちゃんには似合わない。
裕ちゃんの良さもそこにある、裕ちゃんには悲壮感のほうが似合うだろうな。
(軍団という連(つる)みかたは私の性には合わないが。}
トップとしての責任感、慕われる者の苦労や心労はさぞやと思うし,やはり裕ちゃんには「夕陽」ではなく「太陽」でなきゃ、というのは当たり前だから同様に「シャワーと石けんもよく似合う」と言いたい。
思い切り遊んだ(仕事した)後はサッパリしなければいけない。
ずぶ濡れのままじっと乾くのを待つことはない。
健康的に暴れまくるので「くすぶる」ようなこともない。
終われば豪快にビールで乾杯だ。
仲間の面倒をよくみる裕ちゃんだが、ダイナマイトに点火する時、とんびやカラスに気を遣う旭のようなデリカシーはない。
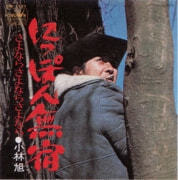
2002/12/04
だれも何気なく歌ってしまっているんでしょうが、
歌う人、聞く人が、いつもちょっとひっかかるところは
「ひろみ」という名前じゃないだろうか、この名前の好きずきは
今は別にして、ひっかっかるならこの「ひろみ」こそが実は
この歌のキモなんである。
さて私には解らないがこの「ひろみ」というのは
このホステスの源氏名か、それとも待たれている男の名か?
わかって歌ってました?
「ひろみ命」なら男だが「ひろみの」と表されると解らなくなるでしょう。
「渚」も「忍」は当然彼女の名だが、よく見るとこういう名の男性はいる。
「ひろみ」という名もどっちともとれる、ここが星野哲朗のすごいところだ。
「ひろみの名前で出ています」ではなく、せっかく「昔の」とはぐらかせているのだから男の名だともとれる。が、
次に「止まり木」に注目したい。
ご存じのようにバーカウンターにある足の長い椅子のことである
鳥が留まる鳥かごに渡す細木も同じだが「留まり木」とも書く。
「止まり木」はいいとして「止まってくれるの待つわ」にも
「止」と書くのは不気味だ。
「ひろみ」が男ならこの流れ女は「ひろみ」を人生の終止符にしようとしている、そんな覚悟だ。
しかしこれだといくら刺し違えてもあからさまにどこかの「ひろみ」さんということで他人事。テレビのワイドショーになってしまう。
こんなふうに男の名が決まっていては歌の世界が狭く軽薄になる。
わざとぼかしてあるんですね、つまりどっちとも解らない方がよいのだ。
名前といえば「アキラ」が男女どちらもありの名というのもこのヒット曲を考えると奇遇だ。
「アキラ」という響きには無国籍という感じもある。まさにさすらい
でも私は漢字の「旭」と書く方が好きなのでこれで通してきた。
中にに九という字ががあり、並べてきた曲名も9曲目。
旭のお住まいは、俗称 九品仏(くほんぶつ)というお寺さんに向いて建っている。

「純子」「女房きどり」
2002/12/06
既に出ているのでタイトルに書かなかったが、
「純子」と「女房きどり」に「オロロン慕情」を加えて
一つの仮説を試みる。例えば、この3曲に登場する男女は
すべて同じ人物である、というのはどうだろう?
これがどうしてあながち荒唐無稽なことではないのだ。
ストーリーに沿えば「女房きどり」「純子」「オロロン慕情」
という順になるが、まず「純子」
歌っている本人(男)は一体何処にいるのだろうと考えたことが
ありますか。言うまでもなくこれは獄中に違いないだろう。
男女の間に物理的な壁がなければこの歌詞は成立しない。
彼はひたすら任期を終え出所を待つ囚人。
次は「女房きどり」だが、この極めて難解な歌詞の疑問は
歌っている本人(男)が自首直前の逃亡犯と仮定すると
いとも簡単に氷解する。
女房などという字面がちょっと年増な女を想像させるが、ハタチ
前後の娘でもおかしくはないわけで、むしろそう考える方が
この歌は微笑ましさが加わって悲しい。
そして「オロロン慕情」はすでにご存じのとおり。つまり
女房をきどる女も、いっしょにカモメの声を聞いたのも純子だ。
付け加えるなら娑婆では「俺」といっている男が獄中では
「僕」となっているのは一貫性としては不自然ではと考えたが
逆にじっと服役を耐えている状況は「僕」のほうが旭らしい。
星野哲朗は遠藤実のこの2曲から「女房きどり」を発想した
のではないだろうか、などと考えるのも又楽しい。
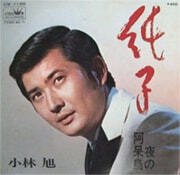
2002/12/06
わずか4行、3番までの歌詞の中に男の人生の普遍性を
盛り込む技に脱帽しないわけにはいかない。普遍性というと
堅苦しいが要するに「今後何百年経っても変わらない」もの
ぐらいに考えればよい。
かつてそうであり、今もそうであり、これからもそうであろう
というようなことである。
「落日」に、なにもそこまで、というアナタも旭の声に酔い、さほど意識もせず歌詞を聞き流しているアナタも2番の4行の歌詞、頭に揃った「生」「知」「落」「恋」男の人生がたった4文字に集約出来るわけはないと思うアナタももしこのうちどれか一つでも欠けたら悔いの残る人生になることは理解できるはずだ。
どれも現実的でずっしりと重い。
しゃらくさいが「ライフ」「インテリジェンス」「スピリット」
そして「エモーション」と言い換えてもいい。
この4点に加え1番と3番に歌われる「死」も外せないという
見方もある、がやはり人はどう生きたかであって
どう死んだかではない。死は単なるピリオド、エンドマークに過ぎない。
だめな男も金欠と失恋くらいでは死ぬことはなかった。
悲しさや絶望感ははむしろ男を優しく強く成長させたものだ。
こういう歌が心底歌われなくなってからだぜ簡単に人を殺めたり自殺するようになってしまったのは。
私にとって旭の演歌は他愛のない戯れ歌なんかではない。
歌詞を解釈することのナンセンスさは承知の上で近づきたいと願う私から旭へのラブコールなのだ。

「さらば冬のカモメ」
2002/12/07
基本的に歌というのは人間の「泣き声」だと考えている。
原因は問わない、嬉しくても悲しくても、感極まっても
人間は泣くからだ。さらに「泣きたいけど我慢する」というのも
泣きの一種だと思っている。ハートが痛くならなくてなにが歌か。
だから私はこれが根底にない歌手を歌手と認めない。
ブルースは歌だがロックはアスレチックだ、
貧乏揺すりかもしれない、汗はかいても涙はでない。
「じゃあ自動車ショー歌はどうなんだ」と言われると困るが
余興も必要でこれはまた後で。すべて余興という連中もいるから
これとは区別しておいてもらいたい。
カモメが旭の心の分身であることはすでに誰でも知っている。
そのカモメに「もう泣かないで さよならしよう」と言っているのだ。
これはただ事ではない。そこに暗示されるのは「死」だ。
女が、「死んでもいい」と言っているが、男もこれにつき合おうとしている。
女に去られても男が死ぬことはないのは「落日」の通りだが
逆にせまられて死ぬことはあり得た。情にほだされると男は弱い。
「わけはきくな」「おれにもわからない」「どうにもならない」
たった一人の女のために、惚れたからにはそれが「だだ」だとて
ぶざまだと言われようと卑怯だと思われたくはない男の心情は
察するに余りある。のっぴきならない展開だが、旭は他の誰よりも
こんな状況を上品で綺麗に歌う。道行きにフラッシュバックのように
並べられる「港・いそしぎ・しぐれ雨」「岬・ブルース・水灯り」
もはや自分の代わりに泣いてくれる分身も愛することができない。
私はこの歌が好きだ
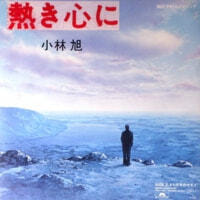
「自動車ショー歌」
2002/12/08
あれこれ、とやかく他人に言うことを旭は得意とはしない。でも
このところ、そんな内容の歌詞や文章もチラホラないではない。
旭にらしくないともいえるが、旭が黙っていられなくなるほど
世の中ひどいことになっていると考えたほうがいい。
ほんとは旭に、こんな事を言わせちゃいけないのだ。
さてこんな前フリで、なぜ「自動車ショー歌」なのか。
滅多にないことだが、これが見事にお説教ソングなんである。
インパクトのあるダジャレで終始するので、つい気が付かない
ということもあるが、各番を要約すれば、「説教しよう歌」だ。
1「ほどほどになさい」2「無理しちゃだめだ」3「怒りますよ」
4「勉強しなさい」ということになる。これは例えば悲壮感漂う訴えの
「海を抱け」とか「文読め若者」「恋せよ乙女」とは基本的に違う。
お説教は、力まず余興ついでにアドバイスというのが旭らしいところだ。
歌詞も含めてこの曲はクルマ好きな旭からは切っても切り離せない
誰もが知る超有名ソングだが、私には未だに解らないところもある。
デボネアはまあいいとしても、「オペルオペルはもうお止し」というのは一体何を掛けた意味だろう。数ある同類ソングにも無理はあるがオペルオペルのように全く意味が解らないというものはないのだが…
また、以前の歌詞に多いのだが、「ダットサン」を「ダットさん」と記してあるものが散見される。
校正ミスとも思えないし、気付かないのだろうか。
「まあこれも余興だよ」と旭は気にしない、かもしれない。
しかし、旭ファンといわれる大滝さん編集CDの歌詞ライナーも「ダットさん」なのは誠に残念である。
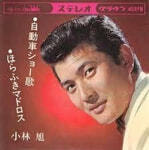
「北へ」
2002/12/08
酒がOKなら「煙草」はどうか。
昨今の、喫煙に対しては旗色が悪い状況になる以前から
一般的にも歌詞に登場することは酒に比べ途端に少ない「煙草」。
旭では「横浜マドロスストーリー」「夢ん中」「真夜中の街角」
「鹿児島オハラ節」など面白いところで登場するが、
使い方の秀逸さにおいてこの「北へ」の右に出る歌はない。
「つけた煙草の吸い殻でアナタの嘘がわかるのよ」という印象的な
歌もあるが煙草にとっては随分不本意な使われ方だと思う。
人称の転換はよく用いられる作詞形体だが、まず1、2番が
「俺」の一人称で語られ、3番がこの男を客観的に眺める3人称だ。
男を空間に放り出すことで、歌に立体感が生まれる、
張りぼての3D・CGなんかには死んでも表現出来ない虚空感、寂寞感、
これほど煙草の似合う綺麗なステージはそうはない。
春から真冬へのグラデーションのような季節変換もみごとだが、
1番に散らばる「咲く」「やすらぎ」「明日」
2番に配した「やさしさ」「愛」「ほほえみ」から一転
3番の「暗い」「傷あと」「あきらめ」「流れる」の世界に
小さく灯る「つけた煙草」がなんと旭によく似合うことか。
旭が自分の中にも、自分の外にも存在していることを知った曲
それが「北へ」だ。
