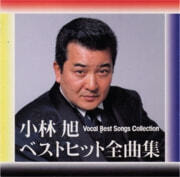ハードボイルド「あれから」
2003/02/23
5000曲くらいあるそうだ。何処かで読んだが、阿久悠の作詞が、である。
毎日1曲ずつ歌っても13年はかかるこの作詞数は普通じゃない。旭の歌だって600以上と知って腰を抜かしたが、自分はそのうちの3分の2を現在まともに聞くことが出来ないでいるというのも間抜けな話で悲しい。
この現実を何とかする方が、ダブルノーベル賞に希望を見ているより何百倍も日本にとっては重要な事じゃないだろうか。
「乾杯」と云えば、長渕剛が今は一般的だが、「きみ」「瞳」(歌詞では「め」と読ませているが)とくれば「カサブランカ」だろう。
ヘミングウェーがその原点だとされるが、どうも情緒表現を抑えたハードボイルドで行こうとすればするるほど、ドラマでは逆にそれが際だってしまう。それならはじめから情緒だけを全面に出したらどうなるかというのが「あれから」なのである。
ごく僅かな例外もあるが一般的に歌詞の中には、舞台空間と装置を表す即物的な小道具である単語「物」が必ずあって、それは例えば街、港、旅路であったり、星、花、雨、ギター、止まり木、酒などだが、これらの装置をいっさい使わずに詞を作るというのがこの時の阿久悠のテーマだったに違いない。
「物」をできる限りそぎ落として、ここに出てくるのは「事」だけである。
いかにも普通ではない彼らしい仕事ではないか。
奥行きを出す為に背景や「物」を置き、イメージを明確にするのだが、ここにはそれを匂わせるものはない、だからこちらとしてはただただ想像力だけが頼りだ。
いったい二日も続けて見た夢とはどんな夢なのだろう、はにかみながら語った大きな夢とはどんな夢だったんだろう。この作詞家はそれを具体的に書かない。
では「具体的に書かなければ解らないじゃないか」というブーイングがあるかといえばそんなことはないのである。
「あれから どこで なにした」と云われれば、わたしたちは誰でも必ず
それこそとめどなく、それぞれの目眩く過去を思わずにはいられない。
さて、情緒だけで作ったような「あれから」はアンチハードボイルドになったか?
この曲で感極まる大男もいると聞くと、湿っぽい歌のようだが、私はそうは思わない。「これから」も続く現実の冷酷・非情さを思いつつ「めぐり逢いのしあわせに乾杯」と歌う旭は十分にハードボイルドである。
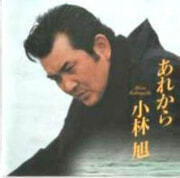
俺には何がある?「日暮れ・行き暮れ」
2003/02/26
この曲の題名「日暮れ・行き暮れ」から反射的に思い浮かぶのは、私にも幼児体験のある 芥川龍之介の短編小説「トロッコ」である。無謀にも一口で例えれば、一緒に出かけた 連れ合いが当然一緒に戻って来てくれると思っていた旅先で「じゃあ、これで失礼」と 何処かに消えた時の「驚愕を伴う孤立感」を描いた、彼の精神の原点を成す傑作だ。
自分の甘さもさることながら、行き暮れた道を一人で戻らねばならぬ自分の情けなさ。
大人ですらこんな帰路に突然出くわせばうろたえるものを、物語の主人公は少年である。 言いしれぬ恐怖感に家にたどり着いたものの、ただ声を出して泣くより他はない心情は そんな極端な幼少の体験が無い者には解らないよと思いきや今、現実はもっと深刻だった。
俺には「夢がある」「友がいる」「唄がある」と力を込めて歌う旭だが、翻って私達に何となくではなく本当に「夢」が、本当の「友」が、本当といえる「歌」があるかと真に 問うた時、実は確信が持てる何物もないと知ったらあなたは「トロッコ少年」です。
今や現実は小説を越えたといわれるように現代にこんな状況はごろごろしているはずだ。 まがりなりにも光さえ見えればそちらの方向へ歩いてゆくことはできる。しかし「夢が無い」「友が無い」「唄が無い」ならばこれは例えば「金が無い」というレベルとは異次元の世界だ。全く光のない世界は自分で灯を点しながらでないと歩けない。
「夢」が「友」が「唄」が無いと知った時、そして自分自身で点した灯はいずれは消える と悟った時、仮にまだその灯は残っていても人が自ら命を絶つことになるのは想像に難く ない。難解なことはなにもない「なんであの人は死んだんだろう」の答えがこれである。
自殺は究極の悪だと考える私も、その苦しみと絶望を思えば避難などできはしない、命を絶つ人の多くは、暗闇の中を頑張って自分で明かりをともし歩いて来た人だ。しかし真っ暗な状況でも光に向かって歩いている人は決して自殺することはない。
「日暮れ・行き暮れ」という状況に必要なものは「光」であるのは自明であろう。
たとえかりそめでもそれが見えるなら幻想でも「夢」「友」「唄」は光である。
ついにこの三つを持てなかった龍之介は(享年35)毒を飲み闇の中で死んだ。
彼の小説は彼自らが闇の中で灯した光の跡である
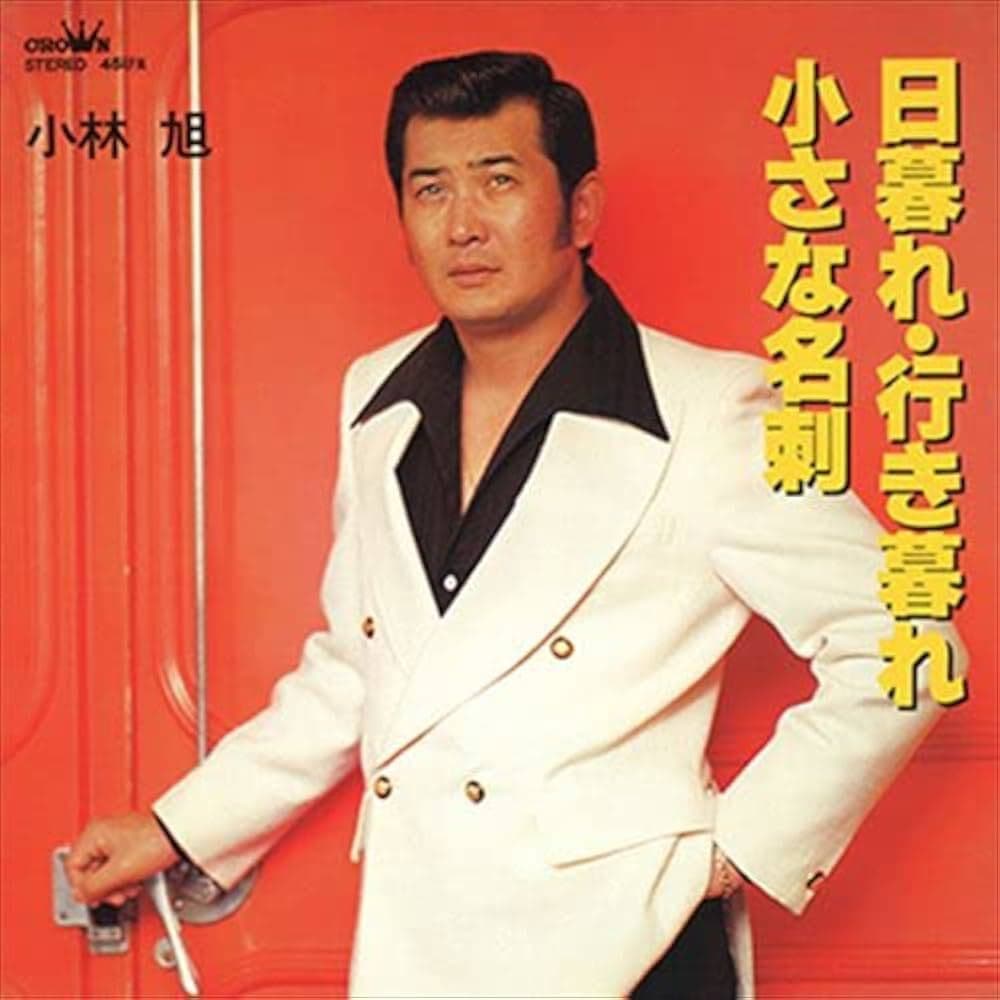
家庭崩壊「水たまり」
2003/02/28
水たまりに映る映像として、最もぴったりしているのは青空とか白い雲だろう。
雨上がりには誰の目にもお馴染みな光景だが、表現としてはちょっと偽善的な感じ。
旭の「水たまり」は、だから夜なんである、念を押す為に「夜」を各番のピリオドにしているわけだ。さて、偽善といえば世間では最もあたりまえなはずの「夫婦」や「家庭」をテーマにした唄が私の聴いた限り、旭の曲には見あたらない。
これは夫婦関係というのが誰もが認める保証されたゴールイン「幸せ」というカタチ、すなわち嘘っぽい「偽善」だからではないのか。全てが仮面夫婦だというのではない、「夫婦」や「家庭」という形態は、どうも歌にすると偽善感が拭えないと言う意味だ。
いきなりだがモノローグの「あいつ」と歌詞の中の「おまえ」とは同じ女ではない。
歌詞の「可憐な俺の花」である「おまえ」は「俺」の実娘、これは親子関係なのだ。
つまり協議離婚をした「俺」が元妻と母方にいる娘を偲んで語り、そして歌う曲です。
「風花」に妹という曲はあったけどこれは我が子、娘さんとはね。
さあ、そうイメージして歌ってみてください。まだぴんと来ない人のために以下補足。
語り1 水面をはねてかき消す夫婦破局のイメージと、時とともに再びフラットな水面に戻る叶わぬ復縁への願い、「あいつ」はそうです別れた女房です。
1番 「あの子の両親は離婚したのよ」との世間の陰口に対する旭の意地。 この離婚で一番悲しみ泣かせた娘、再び戻ってくれる日を夢見る娘への悔やみと愛おしさ。
2番 時に感じる波風の立たない家庭への嫉妬とそんな情けない卑屈な自分への反省。水面に浮かぶ娘の笑顔を泣き顔にしたくない、そっと飛び越えた。
語り2 仮にでも夫婦なら二つあった、家庭なら娘を含めて三つあった影。
一つの影で客観的に気付く自分の欠落感。
3番 敗訴だから「かあさんを大事に」くらいが関の山、狂おしい離縁の日のおまえの顔は忘れようとて忘れられるもんじゃない、今鮮明に水面に浮かび上がる。
もうあなたはこの曲にこれ以外の設定をイメージ出来なくなりましたね。
偽善が匂う「夫婦・家庭」でも崩壊の設定なら旭には「アリ」の、リアルな水たまり。
水たまりと云うより人間を映す鏡と云った方が適切、映る像は心に似て繊細で複雑だ。
「子は親の鏡」とか云うし。
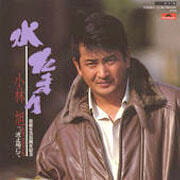
嗚呼!大阪万国博覧会「はぐれ雲」
2003/03/06
山本夏彦は自分の日本史を戦前と戦後で線引きしたが、我々団塊の世代でいえば万博前と万博後といことになるだろう。当時思想的政治的原理で動いていた若者には見えにくかったかもしれないが、文化的見地から世界を眺めていた者にはこの万博が現在に至る日本の新たな出発点であったとする見解に異論はあるまい。
数年前、万博を共通の体体験として持つ友人から「おい、これは一度見ておくべきだぞ」と手渡された1枚の写真があった。パビリオンのすべて消えた緑の丘陵の真ん中に、真っ青な空を背景に立つ「太陽の塔」だった。ご近所では見慣れた塔かもしれない、しかし、30年以上を隔て、いきなり見せられたこの写真には打たれるものがあった。
懐かしさではない、美しさでもない、新しさでもない。それが何だったか今解った。
さすらう旭が歌う「はぐれ雲」が他の曲と少し異なるのは、「人はじっとしていてもさすらっているということがあり得る」ということだ。
「男ひとり、はぐれ雲」と歌われると、雲は男の動きの比喩のようだがそうではない。
「空行く雲、飛ぶ赤とんぼ、沈む夕陽、明日に向かう汽車、川の流れ、揺れるススキ」といった様々な動きに取り囲まれながらもこの男はじっと動かないのだ。
この姿が、「太陽の塔」とぴったり重なった。動かず、じっとしながらもさすらう塔。
背景の空には、はぐれ・ちぎれ・流れ雲がゆく。足元を見下ろしても今は無き様々なパビリオンの面影。てっぺんの金色の面(おもて)を涙のような夕陽が落ちる。
二合徳利にお猪口を横にして乗せたような「太陽の塔」には赤とんぼはよく似合うし、信号もなく渡れぬ川ならぬ高速道路の、今日も東西に行き交う車の流れを見送りながらじっと佇む姿には、野末を渡る風と枯れススキも全く違和感がない。
「男 ひとり」を「太陽の塔 ひとり」とイメージして歌うと、この歌、特に2番は団塊の世代には堪えるはずだ、今にして思えば誰もがあの時代に惚れていたのだ。
東から向かった名神高速道路の左手に、突然現れた万博会場の光り輝く姿を、私は今でも時々夢に見ることがある。あれはやっぱり儚い夢だったんだろうか。
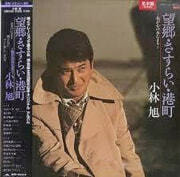
2003/03/08
本日の授業は漢文を含む9教科、なお哲学だけは各8教科個別に講義する。
霧夜娘死 自然科学 意志と表象 ショーペンハウエル
花捧別来 生物学 現象学 フッサール
涙流思抱 生理学 コギトエルゴスム デカルト
生孤独死 心理学 単子(モナド) ライプニッツ
娘愛幸福 倫理学 アンガージュマン サルトル
若命短春 文学 純粋持続 ベルグソン
一人世流 社会学 実存・投企 ハイデッガー
俺時処消 歴史学 純粋理性批判 カント 以上
半分は野暮な冗談だが、半分は本気である。じっくり歌い、鑑賞し修めよう。
これ以上凝縮しようのない語句は歌詞というより、まるで詩吟ではないか。
そぎ落として出てきたこの密度たるや並でないことを、ぜひこの講義で各自
認識して貰いたいものだ、とはいえ講義内容は「高校三年生」レベルである。
まあ硬いことは抜きにしても、本当にこれが歌謡曲か!と思うほどの作品だ。
これは「愛と死を見つめて」といった赤の他人の男女のドラマなんかではない。
たとえば野坂昭如の「ほたるの墓」の兄妹にだって置き換え可能なこの歌詞は、
親しい関係にあるならその相手が動物だとてあり得る、悲しい実相そのもの。
「これは俺には関係ない」と、言える者はこの世には一人もいないではないか。
人ごとではないのだ。身近にある貧富、老若、性別、人格、聖俗、人種、職業、美醜、善悪、そんな人間社会の全ての相対論を消し去り、ここに一つの結論を出しているところも素晴らしい、すなわち「俺もいつかは 何処かで消える」先に逝った者に対し、残った者が同時に自分にも言ってやれる唯一の言葉だ。
このフレーズを美学的に歌声に出来るのは旭をおいて他にない。絶品である。
ぜひエンドレスで聴いてください、まさに日本版ラベルの「ボレロ」です。旭ソングから一曲を選ぶことは私にはできない、しかし仮説として 選ばなければ殺すといわれれば今の私は躊躇なくこれを取る。
「死とは何か?」と訊かれたアインシュタインは、 「モーツァルトが聴けないということだ」と答えたそうだ。 生きているかぎりは旭が聴ける。
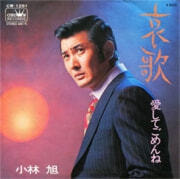
2003/03/17
旭が波濤を越えやって来たのは ジャワである。島のソロという町を流れる川がブンガワンソロ。
留まることなく過ぎゆき決して逆行しない川の流れは古くから時間に喩えられる。陽気なイントロと、スローな歌い出しで表された二つの異なった時間軸。永遠に続くかにみえる歴史としての時間。一瞬にして過ぎる人生としての時間。無限と有限を意識したときから人は動物以上の精神的生物となる。
1番の結句「お日様がにらんでる」と言われ、気づき自制心を取り戻す事の出来た時代がかつてあったことをもうお忘れか。秋田の「なまはげ」の話はどうだろう。
大晦日の夜に突然乱入して来る恐ろしい赤鬼青鬼。泣きわめき母親にしがみつく乳飲み子にこれでもかと出刃包丁を振り回し襲いかかる。幼児期に「この世には母親ですら楯になれない恐ろしいもの」が存在するという事をここでインプットする古人の知恵だ。後々子供の躾には「なまはげが来るぞ」が絶大な効果を持つ。
今の日本には、道を外せば天罰が下るという認識が子供は勿論大人にだって無い。
「一番恐いのは人間だ」から これを抹殺すれば安心というケダモノの時代だ。罪悪感が無くなれば、罰も反省も何の意味もなくなる。
自分の品行を正す「にらみ」を生物である人間は本来自身の内に持ってはいない。「なまはげ体験」で人知を越えた恐怖を知覚する素地が 形成されるのである。なまはげなど存在しないと知る歳になっても恐怖そのものは残っているからこそ「お日様がにらんでる」との忠告に、なにを馬鹿なと思いつつもとてもかなわぬある者に対し畏敬の念を感じることができるのである。
2番の結句「若い時や二度はない」は、文字通り一度の人生を悔い無く生きろと言う意味だが、これを後戻りはないよ慎重にと受け取るか、旅の恥はかき捨てと受け取るかは、「にらみ」を受信するセンサーのあるなしで全く変わってくる。
旭なら1、2番の結句を違和感無く歌い終えるが、これは若輩の台詞ではない。1番と2番の結句がその意味に置いて矛盾しないことを識るのは若年では難しい。
孔子様ですらその年を70歳とみているが、多分、孔子様には「なまはげ体験」がなかったのだろう。
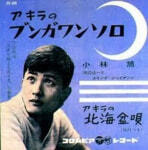
2003/03/19
たとえ実社会で定職に就いていたとしても、心の放浪癖というのは無くならない。
「男は隠者の風格を失ってはならない」と言ったのは確かゴッホだったと思うがそんな心情を旭はいつも代弁してくれる。元来ボヘミアン因子を持つ男という性は幾つになっても「甘えん坊」で「ワガママ」で「非現実な夢」を追うものらしい。
「母の乳房で眠りたい」「すがる涙をふりほどく」「我が行く先をてらすのか」と、この歌詞の1~3番の結句も 男の心の放浪癖をそれぞれドラマチックに言い換えた歌のように思われるが、女性から見れば、単にショーがないオトコの姿にすぎない。
とはいえ、ショーがないと大目に見て貰えるのは男なら誰でもと言うわけじゃない。飽くまでも好意を寄せる男でなければならない。なんでもない男がこのような時は「変態」「人でなし」「穀潰し」が当てはまるのが 心の放浪癖というものである。
好意のない所には理解も同情も無いのであって こうなると誤解をとくのは難しい。
旭ではない私は、なるべく目立たぬようにひっそりと「心の旅」に出るのである。しかしながら、ショーがなくても理解はして貰える男の「甘え・ワガママ」そして「非現実な夢」も、「変態・人でなし・穀潰し」とともに 実は、女性の浅はかな(と言ってまずければ)美しき誤解である。男は女が考えているほど単純ではない。
女性は本物を見抜く直感に優れているが、反面 騙されることも少なくないでしょ。
「母の乳房で眠りたい」=男は最終的にお袋に許して貰えなければ真の安息はない。甘えたいのではなく、おかあさんにはどうしても勝てないという降伏表明である。
「すがる涙をふりほどく」=「おまえを好きだ」、は言い換えれば「おまえ以外は、おまえほど好きではない」だ。男は相手を特定する事の方に後ろめたさを感じる。
「我が行く先をてらすのか」=頼まれれば断れない、むしろ頼まれたほうが燃える。
損得ではない。「採算の取れない事って、どうしてこんなに面白いんでしょうね」と坂本龍一が言っていたが、男の仕事は銭勘定を始めた途端それがつまらなくなる。
さあ世の女性よ、これが男の内に眠る放浪癖の正体だ、100%理解は得られまい。
しかし、もし少しでもわかるなら、旭は今よりももっと魅力的に見えるだろう。こんな非社会的な男こそ実は女性にとって最も惚れ甲斐のある男じゃないのか