ちょっと悲しい「恋の山手線」パート1
2003/01/17
数ある旭のダジャレソングの中でもピカ一の出来であると、私は思う。
双璧ともいえる「自動車ショー歌」に、ほんの僅か有名度では後塵を拝するものの、歌詞の出来映えと曲調はこれに勝るとも劣らない。
御徒町に僅かのこぼれがあるけれど後は完璧、しゃれの踏み形も、外し方も
ユーモラス且つコミカルでキレイにまとまっており、無理がない。
当然駅名は内回りの順番通り、きちんと列んでいる。
1番~5番は、それとなくだが、仕事、お酒、食事、買い物、散策を割り振っていて、それが各駅の実際の性格と合っているのもいい。
元ネタが有ったとて言葉遊びと江戸文化に精通した人ならではの出来だ。
車は一般的なものだが、山手線は東京を代表するファクターでしかないという見方もあるが、「ショー歌」には既に無い車種やメーカーがあり、若い人にはレトロソングの感は否めないだろう。それに比べ山手線は、26駅すべて現役で、この路線なしに東京の存在は有り得ない。
とはいえ、東京人でも26駅全部を答えられる者は案外少ないだろうから、逆に、一発で覚えられるこの歌の価値は大きいといえるだろう。
ただ誠に残念な事にこの歌には不幸な歴史があって、声高に歌えない、というのも事実である。ご存じの通り山手線というのは東京には存在せず、走っているのは「山の手線」なのである、当時は「山手線」であったのは確かなのだが、ある時突然「山の手線」が正式名称なのだということになってしまった。もっとも東京の山の手を周回する路線だからそれで正しいのだが、私には大いに不満だった。
「山手」という場所は横浜にあるので、それと区別する為ともいわれたがそれでも私には、歌とは関係なく納得出来なかったことを思い出す(安易に名前を変えてしまうと、その実態もアイデンティティーもそれにまつわる歴史も思い出も消滅する事が解らんのか)。
古い物が消滅することに何のコダワリも持たない人たちがイニシアティブを取れるところが、悲しいかな東京の自由で魅力的なところなのだろうが…。
歌の方は歌詞を変更される事もなく多分そのままになり現在に至る、ということだろう。だいいち「恋のォ~山の手線」ではせっかくの電車が、走れなくなるばかりかリズム感も損なわれてしまう。
これは変えられぬ、浜庫さんも既に亡い。まして御大小島貞二の作品を汚す事は誰にも出来はしない。
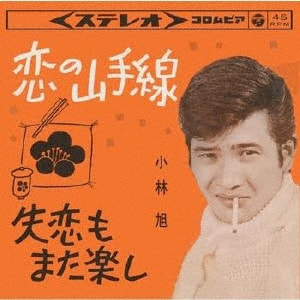
ちょっと悲しい「恋の山手線」パート2
2003/01/17
この歌は、旭にとって地元東京の「ご当地ソング」だ。周知のように旭は根っからの東京人。けれどもどこかで宍戸錠が「旭はローカルの野生美」と、語っているようだが、旭は世田谷生まれの山の手育ち、ローカルといっても
他のカントリーとは全く異なる東京という環境の「ネイティブ・セタガヤン」なんである。以前の武蔵野や世田谷は、カントリーそのものであったが、現在だってそう変わらない。規模は小さいが田畑はまだあちこちで健在だ。
言うまでもなく東京は地方人集合体みたいなものだが、いわゆる江戸っ子は
隅田川・荒川・江戸川エリアに集中していて、一方新興の流入組が多摩川エリアで山の手を形成したわけで、それ以前の世田谷が旭の立脚点といえるだろう。
神奈川湘南という近代的な郊外からやってきて、ステージである東京に都会のイメージを定着させたのが裕次郎である。彼は東京人ではない。
東京の急速な変貌を見てきたに違いない世田谷人には、或種の傍観者的な性格があって、自分の周りで勝手に色々な事が起きるのだが、当事者という感覚が希薄だ。これが良くも悪くも旭の持つ透明感に通じているのではないか。
東京に住んでいながら、ここが首都という自覚がない。山手線の駅のひとつに東京という名の駅があることを殆ど意識したことがない。むしろ奇異に感じる。
東京が何処にあるのかよく解らないような東京人のDNAこそ旭。旭の魅力の源泉がここにある。「実態の見えない東京人」たる旭は、まわりから差し出された衣装とキャラクターをそっと素直に、こだわりなく引き受けたのである。
勿論、その栄光も悲しみも同時に引き受けた。そしてそれを今も全く崩さない。実は、たった一度だけ見た「仁義無き戦い」の旭の顔に、私は「生粋の東京人」のオリジナリティを見る思いだったのだ。
山手線には終点がない。いくら行っても終着のない円環という無限構造は、旭の旅と同じ、あてのない世界、果てのない道。東京は孤独だ、身寄りがない。
東京自身が日本の孤児「さすらい」そのものだ。世田谷人を通してそれが見える。これは私だけが感じる旭への偏見かもしれない、しかしそれでもよいと思う。
旭の顔に時折陰る淋しそうな表情に、「恋の山手線」が持つ、ちょっと悲しいさだめをダブらせてしまうのは、多分私だけだろうから…
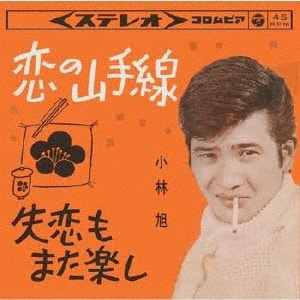
三つの顔を持つ…「わかれの演歌」
2003/01/21
しばらく歌っているうちに、どうもここに登場する男女はそれぞれ別々の3組だと気がついた。別れにも様々なスタイルがある。
「あなた…あなた」と旭が連呼するので、ついこれは連続した別れ話で当然同じ男女かとばかり思っていたがそうではない。
1番は男女別々の方角へ別れてゆくパターン
2番は、向い合ってはいるが心理的な隔たりの出来てしまった別れ
3番は、男が去り、女がとどまる別れ、である。
1番の別れを強調しているのはもちろん西口東口だが、「別れが歩いてくる」とは言い換えれば「お互いが遠退いてゆく」こと、「街灯の後ろ」というのはそれぞれが「後ろ」を向いているからだ。
2番の別れを象徴している単語は、「電話」と「裏窓」だろう。
インタラクティブだが隔たりのある電話、外は見えるがそこは表通りではない裏窓。
3番は「雲のきれま」と「なみだ恋」「見送り」で、ここからは手の届かない雲。
なみだ恋は、別れに対して「なみだ乞い」、ひたすら受け身を暗喩する。
見送りは、説明不要だろう。
ここに登場する3人の男達は思い詰めた女達に対しみな冷たくそっけない。
旭のように止むを得ず「愛していりゃこそ」という種類の男達ではなさそうだ。
「わらって別れてきたぜ」と旭なら苦し紛れな言い方はするが「わらってさすらいに」なんて旭のニセ者にちがいない。
ここでは当然旭は女、一人三役である。旭の演歌はいいなあ。
ウエットな歌なのに声にじめじめ感やべたべた感が全くない。
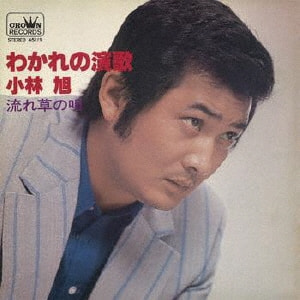
ド、ド、ド ドレガ女?「アキラのジーンときちゃうぜ」
2003/01/24
ジーンとくるとは、例えば裕ちゃんの場合は「小島の秋」だったりするわけで何となく感傷的になり目頭が熱くなるというような感じを表す言葉だ、単純である。ところがアキラのジーンと来るシチュエーションは複雑だ。
旭の歌詞の特長である「まるで迷宮に迷い込んだが如き世界」にようこそ。
登場人物はたぶん2人だと思われるが3人かもしれない、いや4人かも。
まず主人公は「オイラ」、これはまあ旭だとして、そして「あの娘」
加えて「こいつ」と「あいつ」である。
友だちの「こいつ」とはオンザロックまたは気に入りグラスの事であるとするなら3人、「あいつ」とは「あの娘」の代名詞だとすれば2人、ところが大人のふりして「あいつ」が「オイラにまかせな」というところから混乱がはじまる、えっ!「オイラ」って誰?。「ベニスに死す」みたいな美少年かも。
ジーンとくるのは冷たいオンザロックだと思うのだが、「あの娘みたいに」
ジーンとくるあの娘の手にもロックのグラスがあって、この娘は「大人のふり」をしているのだから未成年でウイスキーは飲めないわけで、ふざけて旭のマネをして「オイラにまかせな」といっているんだろうか?多分そう言うことだとして、「旭は、ジーンと来るロックを持って旭のマネするあの娘みたいにジーンと来る
ロックを持っている」ということになるのだろうか?まるで鏡地獄のようだ。
でも「気に入りグラスで片手にホワイトたっぷり注げば」片手はホワイトで
びしょびしょになってしまう。「グラスを片手に」あるいは「グラスに片手で」じゃないところがすごい。こんな混乱の中から立ち上がるのがなんとも陽気でたのしい楽曲の世界なわけで、「乗り」は寸分も狂ってはいない。ピシッ、ピシッときまったスカパラのブラスが旭の「お酒スタイル」をシンボリックに表現している。
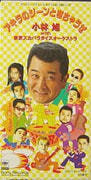
さあ おとうさんオムツ替えましょう「氷雨」
2003/01/25
この歌が作られた30年ほど前に、老人介護が国政問題になるなんて考えた人間がいただろうか。思えば高度成長の真っ直中、両親は勿論爺さん婆さんなんて思考の外にすらいなかった。
悲しいかなビジネスになるんじゃないかとの不純な見地から、ようやくここに来て老人の介護をする体制が整いつつあるように見えるがどれ程の物か。実の子ですら手を焼く介護、犬の散歩を理由に他人に任せ、金で解決しようとしても、ろくなサポートはないと知るべきだ。
「介護される方」ではなく「介護する方」の環境も体制も劣悪だ。
だれもが率先して介護したくなるようなカッコいいデザインの車椅子があるか。
おもわず下の世話をしたくなるようなサニタリーがあるか。
何回でも身体を動かしてやりたくなるようなゲーム感覚のベッドがあるか。
そして何より「どうしても介護してやりたくなるような老人」になる勉強をするつもりがあるか。これからは義務教育として確立すべきではないのか。
実際、「介護される」マナーが年寄りに欠けているのである、「老人のの尊厳」とかなんとか解ったようなことをいうが、この寝たきりの老人が平気で、介護する者の尊厳を傷つけることを言うのである。多分不甲斐なさからの言葉だろうが、こちらとしてはただ介護するしか為すすべもなく「荒む気持ち」で寝たきりの寂しさを、悲しさを受け止めるしかない、こっちだって「傷だらけの心」。
しかしこれは老人の責任ではない。長寿国がはじめて直面する「氷雨」。
核家族はそういうことを学んで来なかったのである、これからは違う。
色恋を離れた人の世を書かせるとこの作詞家は、本質を突いてくるのはすでに「巷の子守唄」でもおわかりだろう。
歌謡曲と言っても旭の歌はロンリーウルフや女心、男女関係ばかりではない。一見、人情話、浪花節、童謡を装うが人間の現実そのものを俎上に乗せる歌があるのは流石である。
旭は、松尾芭蕉の「野ざらし紀行」にも通じるこの人間の「無力さ」「どうしようもなさ」の境地を歌い、歌うことで救いを希求する。
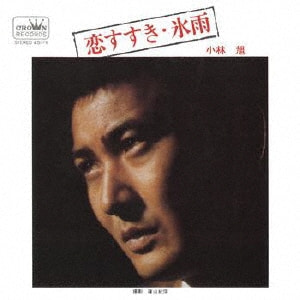
枯れてはいない「乾いた花びら」
2003/02/04
「~しておやり」と云う言葉には語感に、なぜか優しさがあって好きだ。
とかく「~してやる」というと恩着せがましく「もの持てる者」の思い上がりと感じられなくもないが、この曲に出てくる「愛しておやりよ」「包んでおやり」「話しておやりよ」「聞かせておやり」には、施してやれとか恵んでやれという傲慢なニュアンスはない。
旭からこのセリフを聞かされると「俺にも何か出来るかもしれない」と背中をぽんと押されたような気がするから不思議だ。
と同時に「こりゃ何かしなけりゃまずいな」という気持ちにもさせられる。
何故かといえば、旭がいつも「そうしてあげなさい」という誰かからの声を聞いていて忠実にそれを実行しているからだ。
涙は「涸れ」ても、花はまだ「枯れ」ていない、さすが阿久悠選ぶ言葉に間違いはない。さあ、水をやれるのはおまえさんなんだよ。
ふと、人間の才能、例えば歌が上手に歌える才能というのは一体何の為に有るのだろうかと考えることがある。
同じ人間でも、歌の上手い人下手な人、声のいい人悪い人、
さらには声そのものを初めから持たぬ人もいるのに。
才能は当人の実力を誇示する為にあるのではない、たまたまその人に授けられた能力に過ぎないのだ、この能力は実は自分のものであって自分のものではない。
ステージに立つということは云ってみれば生け贄である。みんなに代わって人間とはこういう素晴らしい歌を歌う生き物だと云うことを示すこと。
歌手にはその使命があり、「選ばれて才能を授けられた」との自覚がなければならない。ステージに立った歌手は「私の歌を聞いてください」ではない。「私の歌を聴け」でもない。ましてや「歌って差し上げる」でも「歌でもどうぞ」なんかでない。「みんなの代わりに歌います」なのだ。
だからこそ一回一回が真剣勝負。私のミスが私のミスではないのだから背負ったものは重い。持てる能力を己の為に行使するのではなく、力のない者のかわりに行使してこそ「まごころ」なんである。
何かが出来るかもしれない人は、それが出来ない人の代わりに存在している。
「旭よ!みんなに代わって、お前が上手に歌っておやりよ、お前ならそれができるよ」そんな何処かからの声を旭はきっと聞いているはずだ。
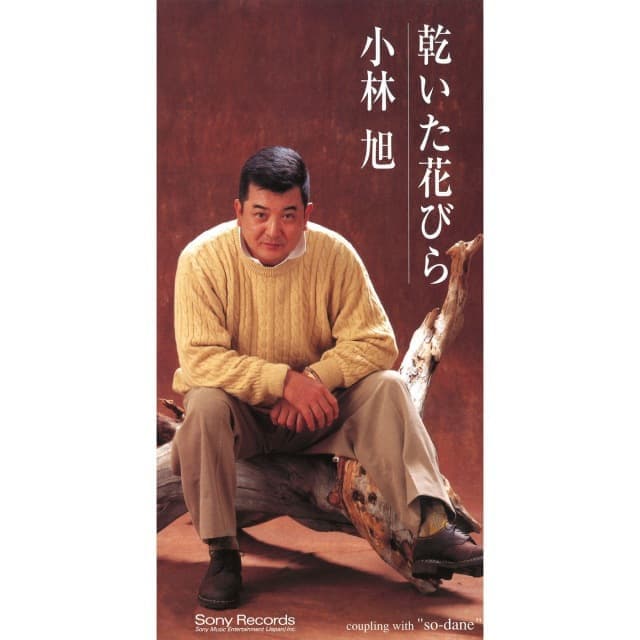
トニー「おまえに逢いたい」
2003/02/19
ことある毎に「ダーリン」だの「ハニー」だの「アイラブユー」などと臆面もなく口にするアメリカ人と異なり、日本男児は感情をストレートに口にすることが苦手だ。
云いたい気持ちがない訳じゃなく、単に照れくさいだけなのかもしれない。実は、大声で本音が吐けたらどんなにいいだろうと思っているのは、日本人だって同じだ。
若い人と違って面と向かっては、なかなか言えない言葉も、歌ならそれができる。かなりきわどい言い回しだって歌詞ならお小言を頂戴することもあまりないし大目に見て貰えるから不思議である。
人生には「離ればなれ」という状況は山ほどあって、相手を恋しく思うのはなにも若い男女だけとは限らないのは、わかっていながら「おまえに逢いたい」と歌われると恋歌と思ってしまうのは、これまで自分が歌というものに肉声を託すという経験も、体験もしてこなかったからだと、旭のこの歌を聴いて初めて気が付いた。
3番まであるこの歌は、それぞれ異なった「おまえ」に逢いたいと歌う3種類の別離である。1番は友、2番は女、3番は肉親。これをてっきり今まで全て女だと思っていた。
同じ場所、同じ時、共に楽しい体験をした者は全て友である、そんな過去があの時の歌で蘇る、既にこの世にいなくたって、おまえに今逢えたらどんなに嬉しいだろう(1番)。
遠距離恋愛でもいい、単身赴任の夫婦でもいい、二人の間を引き離す様々な状況を越えて熱い思いが募る(2番)。
幾つになっても親は親、元気でやっているだろうか、ひもじい思いをしているんじゃないだろうか、そんなことばかり考えてしまう。便りもないけれど、逢って元気な声と笑顔をみてみたい(3番)
「おまえに逢いたい」と言う気持ちは性別、年齢を問わない。
これは、あなたの歌だ、照れずに大きな声で思い切り歌え!
