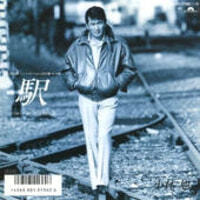「惚れた女が死んだ夜は」
2002/12/09
時間というものは、面白いもので電車を待つ5分は恐ろしく長い。
しかしわずか10回歌えば、即リピートでも50数分が経過するこの曲、
用賀インターから東名を走れば御殿場まで来てしまう。人生は短い。
旭の歌の中でも長い曲だから1時間でたった十数回しか聞けない。
時間は飛ぶように過ぎる。旭の歌の密度はとにかく濃い。
死んだ女を「甘えてすがった さみしがり」と歌う男の方が逆に100%
目一杯の甘えを露呈させるこの曲は、泣きの入り方でも異色である。
実際こんな甘えには、周囲の同情も期待出来ないだろう。
見るに耐えない、聞くに耐えない男の姿を歌って成功する確率は極めて低い。
この歌は「聞く歌」ではない、「聞かせる歌」ではさらにない。「歌う歌」なのである。この歌で「聞く5分」と「歌う5分」を実感して貰いたい。
見るに、聞くに耐えないものは人に晒さないのが慎みというものだが
こんなとき「慎み」がなんだ、という気持ちだってあってこそ人間。
人生には誰にも聞かせたくない歌を、歌うことだってあるだろう。
「聞かせる歌」ではない歌を歌っていい男は勿論旭以外には、ない。
だからこれはカラオケで歌ってはいけない、他人に聞かせてはいけない。
当然思い切り外してかまわない、そのためにあなたの横には旭がいる。
旭と二人だけで歌うこの歌の味わいと時間はきっと濃い。何十回歌っても。

2002/12/09
カクテルというのは、ふつうシェーカーに入れて作るもの
「恋のカクテル シェーカーで作りゃ」もしくは
「恋のシェーカーで カクテル作りゃ」ではないか。
出来たカクテルをまたシェーカーにいれちゃ、こりゃさかさまだ。
おやまあ、カクテルに酔ったか、恋に酔ったか、旭の声に酔ったか。
倒置法というやりかたは歌詞ではもっとも一般的だが、
時間軸が逆転しているものはめずらしい、まあ理屈じゃないんだね恋は。
そう思って歌詞をよくみると、この曲は3番とも全編逆さまにフレーズを追っても成立するツーレロソングだ。いやむしろ逆さまに追った方が論理的だ。
1番「久しぶりに来たラブレターにときめいている俺を笑わば、笑え、
中に入っていたのが写真だとて抱きしめてキスもするし、話もするぞ。」
2番「背中合わせじゃ相合い傘だって濡れるじゃないかこっちをお向きよ、せっかくロマンチックなデートだったのにすねるなよ、好きなくせに」
3番「恋敵が現れりゃ振られて泣き別れなんてことも、それを思えばいっそ身を引こうか、でも今の二人にゃそりゃ無理だ、ああ参ったな」

2002/12/10
国語の時間にこういう俳句を作った生徒に良い点数をつける先生は今の学校にいるだろうか?
いない、と私は思う。誰だってこれではさっぱり意味がわからない。
ところがこの、なんともばらけた単語からなるワンフレーズから夜の女を歌った歌詞を作ってみようと出発し、出来上がったのが「アザミ白書」ではないか、と私は思う。
阿久悠の得意技なのだが、まず「土砂降り」をもとに
1番に「水割り」を、2番に「爪切り」を充てる。
韻を踏むのは皆さんラップでもお馴染みだが、逆引き広辞苑でテキトーに探してくるのとは訳が違うのはこれからだ。
娘から始まる女の足跡を花にたとえ「れんげ草・夕顔・あざみ」と荒んでいく心境を描写、歩いてきたというより勝手に自分を運んでゆく「時間」の恨めしさを「変わる真夜中・のびる爪、誕生日」に象徴させている。
さらにこの冷酷な時の流れにシンクロするように音のニュアンスでも「かたりと氷の溶ける音・パチンと爪を切る音・ざんざん降りの音」と鋭さ、激しさを変化させてゆく。
トゲとはいっても現実には非力なあざみ
こんな陰画のような女の人生のパースペクティブの中で登場するのが
「土砂降りで ふと思い出す 誕生日」の一行である。
なんと寂しいかな、しがない夜の女の独りぽっちのバースデー、しかも祝うべき日を、なにあろうこのひどい天気で思い出す自分の情けなさ。
まさに阿久悠マジックだが、しかしこれでは終わらない四季のリング。
あざみという花は秋から春にかけて咲く多年草である。
多年草は、冬枯れるが根は残り、春にまた復活する樹木のような草花だ。
「わかれ道」にだって四季は同じように巡り来る「冬の向こうに春がある」。
はたちはとうに越したが、ケーキのローソクの炎は赤い。
「土砂降り」と「炎」のコントラストはここまで来るともはや感動ものだ。
「女は強い」
こういう曲を旭に作り歌わせた阿久悠と小林亜星にわたしはエールを送る。
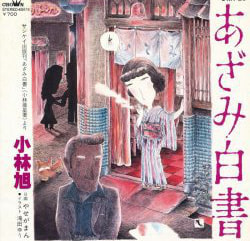
2002/12/11
これほど返すのに時間がかかっている歌はない。
ああ懐かしの「ダンチョネ節」。
「星海峡」は島を去った男への、今度は島に残した女からの返歌である。
「おいおいお、何を言い出すかと思えば、何処が返歌だ」とおっしゃるのも無理はない。テンポもムードも、なにより味覚が、口当たりが醤油とマヨネーズくらい違う。だからいいのだ。
さあ「星海峡」を見てください、「風に揺れる椿」が目に入った人は鋭い。
そう冒頭にに出てくる「昔の歌」こそ「ダンチョネ節」のことである。
ダンチョネ節は快晴、星海峡は夜霧という設定の違いがそれぞれ男女の心象風景として決まっているし、使い方は異なるが「風」と「うらみ」の表現、女の「いやだ やだ やだ」と男の「口笛」のSE 、「小島のカモメ」に対応する「夢よ飛んでけ」など取りこぼしが全くない。
これがどうして返歌ではないと言えるだろうか。比べれば比べるほど、
写真のポジとネガのように、この2曲はぴたりと重なるではないか。
まさしく「断腸の思い」だった別れが時を経て蘇る。
2曲の間に横たわる二十数年という歳月を、なによりも同じ旭の声で聞く幸せ、陳腐だが「生きていてよかった」というのはこういうことを言うのだ。
じっくり聞き比べ、歌い比べてみたい。
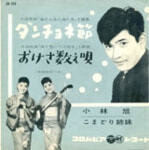
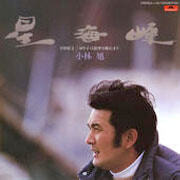
2002/12/12
たまには作ってやろうと思う作詞家だっている。
別に意地悪なんかではなく、クリエーターなら当然だろう。
これでうまくいくとの保証は少ないからこれも冒険である。
旭は、他のシンガーに比べ歌詞カテゴリーの豊富さでもダントツで
それも、単に器用にこなすというレベルをはるかに超えている。
作る側がひとつ冒険してみようかと考えたって不思議じゃない。
言葉の専門家なら、いろんな断片的フレーズを、いくつもの
引き出しに、閃きのかけらとしてしまい込んでいるはずだ。
それをランダムに取り出し、書き連ねる、文脈が通っていないほど
面白いんじゃないかというように、つじつまをわざとあわせない。
1番だけを見ても、それぞれが全く脈絡のない4つのフレーズは、
これをもとに1曲作れそうな独立したムードを持っている、
2番も含めれば7曲ぐらいは出来そうだ、「書いた数だけ幸せに」
と言うものでもないがこれはかなり贅沢な曲かも知れない。
「おまえの心の 小さな花びらが ほのかに女の 香りをつけて」(叙情の章)
「紅ひく仕草が 絵になるこんな夜---」(夜の巷の章)
「おまえは空行く 雲になれ---」(放浪の章)
「泣いた数だけ 倖せに なれるじゃないか」(銀幕の章)
「やさしいオクレ毛に----笑ってオクレ」(楽宴の章)
まるで冗談みたい、とても一つの歌とは思えない。繋がらないでしょう全部が。
作詞家はそれでいい、でもこれにメロディーを乗せろと作曲家にいうのは酷だ。
内容を自分なりに解釈して曲づくりする作曲家なら多分頭の中がパニックだ。
現代音楽にはテープの逆回しなんてのもあるけど支離滅裂じゃ歌えない。
だからアドリブ的歌詞の冒険のオトシマエは自分でつけなければいけない。
作詞家 中村泰士がこの歌詞に自分で曲をつけたのは言うまでもない。
そして歌詞にその声で命を吹き込むのが旭だ。全く違和感がないどころか不思議な雰囲気と味わいのある一曲として歌い上げる。
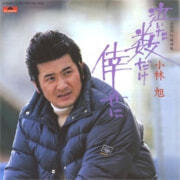
2002/12/13
今更特に言う程のことでもない。
作詞家はそれを知っているのか旭の曲は「らりるれろ」を含むフレーズが
ほんとうに多い。ら行を含む単語をあえて選んでいるようにも思える。
他の歌謡曲を調べたわけではないが、そんなことはどうでもいい。
「旭の声」で歌われる「旭の曲」に多いということに意味があるのだ。
「さすらい」と「思い出酔っぱらい」、これも異色の組み合わでしょう?
語尾で揃えて選んだわけではない、この2曲異様に「ら行」の密度が高い。
「さすらい」では「過ぎてゆくのさ 夜風のように」の行以外全行に(題名も)「ら行」の字を含んでいる、実際歌ってみるとこの歌の隠し味は「ら行」なのではないかと思えてくる。「ら音」がキラキラと輝いている。
同じく「思い出酔っぱらい」も「指輪外して ため息ついて」の行以外全行に「ら行」の字を含む、というより「ら行」を楽しんでいる気配さえ伺える。
(「腕に虹だけ」も同様に「ら行」を多用させているが、題名には含まれない)「ひゅるり・からり・ほろり」と擬音で攻めまくる「思い出酔っぱらい」はもはや確信犯である。「さすらい」とはテンポもリズムも全く異なるが調べ始めたのは、この「思い出酔っぱらい」が歌っていて調子がいい理由は「ら行」のせいだと気付いたからだ。このルーツは何処かにある、と考えて行き着いたのが「さすらい」だ。「ら行」の歴史は古い。
今のところすべての行に「ら行」がある歌は見つけられないが、「指輪」を「リング」と歌えば「思い出酔っぱらい」はパーフェクトということになる。
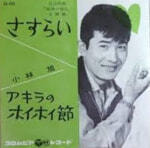
2002/12/14
なんてったって「さあ、元気をだせよ」と親しい人に言って貰うほど
効果のあることはない。
「元気をだせよ」と言うつもりで「ガンバレよ」という言い方があるが
これは、今の状態を維持するかさらにアップせよと言っているわけで、限界に達している人には、無責任な脅迫にこそなれ励ましにはならない。
もうそれはいいから方向転換への勇気を持てというのが正しい。
旭の人の励まし方は「身の上ばなし」が基本だ。
「身の上話なんて するなよ」(落ち込むなよ)でアプローチ
「---したってさ」(落ち込んだって意味がない)で寄り添い
「---ときにはね」(元気を出せよ)で方向転換のパワー注入。
「惜別の歌」「風花」の慰め方も時代を超越して
「悲しむなかれ」「わが友よ」「旅の衣をととのえよ」
「ともかくおやすみ」「叱りやしないよ」「春は必ず来るんだよ」と
同様のパターンだ、相手の性別、肉親を問わないこともわかる。
こうして人を励ます旭だが、そんな旭の歌を聞くわれわれも同様に
励まされるのは何故だろう、旭は直接私たちに向かって「元気をお出し」
とは言っていないにもかかわらずである。理由は彼の絶対的な孤独にある。
ひとりぽっちの寂しさを誰よりも知っている旭、
実はそんな旭を励ますすべを私たちが持っていないことに気が付く。
彼は永遠に励ましをもらえる側にいないのだ。
たった一人ですべての人の悲しみを背負いゴルゴダの丘に登る
キリストの姿に旭を重ねるのは、唐突過ぎるだろうか?
キリストを男のダンディズムの極致と言った人がいるが、
私にとって旭は男のダンディズムのシンボルだ。
そういう人間が存在するということが、無言のうちに私を励ますのだ。
黙って酒だけ置いてゆこうか…。クリスマスが近い。
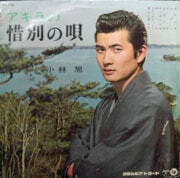
俺とお前「夜の旅人」
2002/12/14 (管理人のリクエストに応えて頂きました)
男なら誰だって、自分の人生のエンディングを夢想しない者はいないだろう。その時のエンディングテーマにこの曲を使いたいと、この曲を聞くたびに思う。逆に、この曲がおしまいに流れて、決まるストーリーにはどんなものがいいだろうと、考えたりもする。この曲がエンディングで似合うような、人生を思う。
「さすらい」では思い出をつれ、泣かせに来た「夜」が、今はその涙を隠しにやって来る。そんな人生を送らせてもらった何者かに憎しみをも含めて感謝せざるを得ないような歌、誰にも看取られなくていい、暗転と同時にこの歌がタイトルバックで始まれば、畳の上で死ねなくたっていいと感じさせる歌、センチメンタリズムと笑わば笑え。
このうねるようなサウンドを浴びるように、ヘッドフォンで聞け。たった一人で。文句ないイントロ、旭の歌う顔、唇の動きまではっきりと「見える声」が目の前に現れたら心が、そして体が震え出すのを止めることが出来ないだろう。
まるでモーツァルトのコンチェルトのように、その声はある時はオーケストラを引っ張り、いたわり、ある時は絡み、殴り込み、歩調を合わせ、悲鳴にも似たブラスサウンドが嵐の如く降り注ぐ中をゆっくり消滅に向かって移動する。
襟を立てた着古しのトレンチコートのようなギターのチョーキング。
心臓の鼓動に呼応するチョッパーベース、孤独、後悔、未練、思い出、情熱そして夢。
その一つ一つのひだに優しいピアノが香りを添える。
作詞・作曲もそうだが、編曲もこういう伴奏を聞くと大したものだと思わざるを得ない。
バックでもない、手前でもない、まさに旭と「伴に奏でる」さすらい人のレクイエム。
ところが見回しても、自分で自分をいたわりながら生きてきた夜の旅人に、同伴者はいない。「俺」と一緒に歩く「おまえ」は、実は俺自身なのだから。
しかし旭はこんな旅人が決して自分一人じゃない事を誰よりもよく知っている。そして「命を粗末にするな」と言っている。
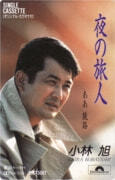
ああ「昭和恋唄」
2002/12/15
若い頃には全く意識もしていなかったのに、年を経(へ)て振り返れば
残酷で無情な時の流れを思わざるをえない。そして過去のなんと愛しい事よ。
阿久悠が「昭和恋唄」の1番と、2番のあたまにそれぞれ「いのち」と「とき」をもってきたのには意味がある。なんで「恋歌」じゃなく「恋唄」なんだ。
私は、この歌詞を構成する単語を一端ばらばらにして、その「いのち」と「とき」でくくってみた、子どもがよくやる言葉遊び「仲良し・仲間はずれ」だ。
いのち「生き、花、おとめ、おとこ、おとな、こども、わたし、咲く、生まれた、あのこ、あのひと、人」が仲良し。
とき「昭和、競う、みじかい、十八、ハタチ、境、遠くなる、時代、真ん中、過ぎた頃、1日、巡り逢う、この世、満たす、流す」が仲良し。
なんと歌詞単語の80%なんである。
「いのち」と「とき」は仲間ではない、と言うためのテクニック、半端じゃない。
しかし、これだけでは旭は歌えない。その答えは残りの20%にあるのだ。
「恋、情、悔、信、抱、涙、知、飢」が残った。
では、この単語をくくれるキーワードはなんだろう。
「いのち」そのものは「とき」からみれば、風や嵐とおんなじ自然現象にすぎない。
「とき」の流れの中にほんの一滴落とされた「いのち」を表現するためのもう一つのキーワード、それは「こころ」ではないだろうか、
ところが「こころ」は歌詞の中のには何処を探しても、ない。そう「昭和恋唄」は2番まで、3番がない、あたまに「こころ」をつけ3番まで作らないところがこの作詞家の真骨頂なのである。
一番メインの「こころ」をわざと外すことによって彼は、命ははてても「心」は永遠だと、言いたかったに違いない。「恋歌」では単なるラブソング、「恋唄」でこそ保てる
客観性。まさにそんな曲になった。思い返せば、ああ昭和。
金や、物だけで波に乗り、いたずらに年を重ねてきた者にこの唄を歌う資格はない。
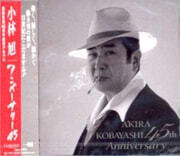
松岡さんに心をこめて「駅」
2002/12/15
どうだ、いい歌だろ、俺も好きなんだ」と旭がちょっと微笑みながら言っている少しマジな顔になって「でもこれは演技じゃないぜ」とも言っている、
「おまえしか見ていないもんな」。
「そうだね旭さんわかってるよ、これはあんたが自分でこさえた「駅」だろう?そこに僕もいるようだよ」
「俺が、お前を呼んだんだ 来ると思ったぜ」
「旭さん、僕はね ずっとあんたを生き、あんたに生かされてきたんだよ」
「知ってるよ、いつだっておまえ俺の前じゃ心も素っぴんで立ってるじゃないか」
「恥ずかしいのわすれちゃうんだよ、でもここまで来ちゃうと、みんなばれちゃうな」
「いいじゃねえか、今が一番まともだよ」
「少しこのまま、いっしょにホームにいたいなあ」
「そりゃいいが、たった4分しかないぜ」
「かまわないよ僕にはいつだって、この時間が永遠だ」
「カッコつけるんじゃないよ、いいことなんてひとつもしなかったな、お前、あげられるものはいっぱいあったのに渡せなかったな」
「…… …」
「でも、もう戻れないぜ。追いつきゃしない、あいつの背中すら見えていなかった」
「旭さん、俺どうしたらいいんだろ」
「過去と未来ばかり気にかけて今を生きるのが苦手なんて言って、後悔してるのか?
似合わねえよおまえには、レールが錆びるのを一番良く知っていたのはお前だろう。なあ、あんときのあいつの目を覚えているかい?孤独なんてたかがしれている。気づきもしなかったろう、いつかあいつが言っていたのは、この事だったんだよ
犬のやつのことなんかまともに考えたことなかったろう」
「そりゃないよ、僕を呼んだんじゃないのかい、いっしょにつれてってくれよ」
「俺を行かせたのはお前だぜ、俺はお前じゃないか?」
「ほんとは一緒に行けないのは判ってる、おれはどうしたらいい?」
「舵を取る資格がないのは知ってるだろう、だったら感謝して乗せて貰えよ」