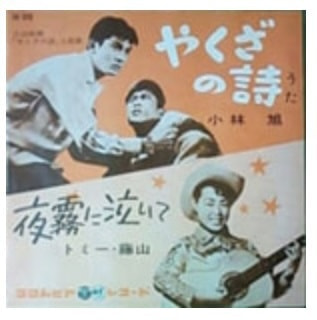2003/01/05
ついて来る見込みが無くてもあっても、10回もあるフレーズはくどくないか。
女にその気があるのなら、こんなにも何度も言わなくても、こんなにくどいくらいの念を入れなくても「ついてくるかい」は一言でいいはずである。
目に浮かぶのは、どうしても、もう帰るはずのない死人に、繰り言のように訴えている構図だ。(「ごめんね」も数が多いが、語数割合ではかなわない)
私の結論はやっぱりこの女は死んでいるとしか考えざるを得ない。
そして、そう考えて歌詞を追ってみると少しも矛盾点はない、どころかしっくり情景が現れるではないか。3番それぞれのサビを検証してみよう。
「君を愛していればこそ 生まれ変われた僕のさ」というセリフは生きてる相手に対して言う言葉としては不自然である。
「君を愛することで僕は生まれ変わったよ」でよいところを「生まれ変われた」と表現させて「せっかく生まれ変われたのに」と悔やんだ言い回しになっている。生まれ変わったことを悔やむのはどうもへんだ。
「身体の弱い君なのに 苦労をかけてすまないね」これもおかしい。
苦労をかけたのだったらすでに彼女は旭に、ついて来て「いた」のではないか。
多分この苦労が祟って彼女は亡くなったのだと解釈していい。
さて「なんでそんなにかわいい瞳(め)で僕をみつめて泣かすのさ」である。
ここまでくればもはやお分かりであろう、これは彼女の遺影、写真である。
「目」と書かず「瞳」と表現しているのは、実際に見つめ合っている構図でなく印刷された顔に対しての絵画的な表現にしたかったためであろう。
どうも遠藤実は「死」乃至は「断絶」という絶体絶命パターンを好むようだ。
女が生きていれば、彼女はきっと間違いなく旭に、ついてきただろう。
そういう女が死んでしまったのである。そうであるなら痛恨極まりなし、過去が有ろうが無かろうが、無一文であろうが、噂が有ろうが無かろうが、もうどうしたって死んでしまっては、ついてくることはできないそんな女に「ついてくるかい」と100回言ったって決してくどいなんてことはない。
そうやって歌う最後のフレーズ「あしたからふたり どこまでもふたり」は「惚れた女が死んだ夜は」とはまた異なった、旭の「涙の歌」の切なさのまた別の表情として、心に刻みたい。
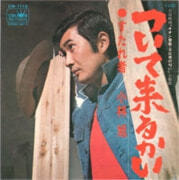
原点消失「北帰行」
2003/01/08
不思議な歌である。
「北へ、帰り行く」 明確に北と明示されているにも関わらず、あてが定まらぬ方向感覚はどこからくるのか。
初めて聞いたホヤホヤの小学生だった頃から40年以上を経た今改めて、じっくり聞き直してもこの印象は全く変わらない。
あの頃から既に新曲という感じはなく、随分古びた詞を歌うお兄さんがいるもんだなあという印象がある。年齢に関わらず人間の本質を突くようなものをこの歌が内包しているからだろう。
その本質とは「帰る」という事である。「蛙は、かえろー・かえろーって啼くけれど、じゃあ帰る所がない者はいったい何処に帰ればいいんだろう」
唐十郎のお芝居か、歌にこんなセリフがあった。原点に戻ることを「帰る」というのなら、その原点とは一体何処を指して帰省地というのか?
そんなものを人間は持っているのか?という問いに、はたと考え込んでしまった事がある。体内回帰という言葉が流行った頃で、「母親のお腹に戻りたいという願望が行動原理になる」と青臭く捲し立てていた学生の頃が懐かしい。
語数少なく、平易な歌詞の中に「重い」単語が2つある。恩愛・祖国である。旭の歌は単語の使い回しが当たり前だが、この二つの単語は旭全歌にワイルド検索を掛けても、ヒット数は殆どないんじゃないかと思う。「恩愛」には身内・肉親の愛情、「祖国」には生まれ育った国という意味があり、ともにその人の原点をも表す言葉だ。「帰る」というのなら、ここがその場所のはずである。
にも関わらず「さらば祖国・恩愛われを去りぬ」とは、一体どういうことか?こんな旭が帰って行く北とは何処なのか?
恐らくこれが、この歌の持つさすらい感覚の源なのだろう。
我々は考えてみれば実は何処から来たかを知ってはいない。
死ぬ場所は正確に特定出来ても、生まれた場所、時間は把握出来ない。
あると錯覚しているだけで、もともと帰る場所など持っていない。
子供心にふと感じたこの歌に対する寂寞感は、本来誰もがもっている個としての人間の孤独に根ざすものであるから、時を越えているのだ。
こんな内容でありながら学生の作らしく起承転結で綺麗にまとまった4行詩、更に、昨日今日明日と時間軸に乗せた1~3番。クラシックたる資格十分だ。
私もそれに倣って、語ろうとしたが、さすらう旭の如く、自分でもわからぬ
方角へ行ってしまいそうである。
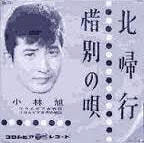
幼なじみのあの歌この歌「落日のシャイアン」
2003/01/09
デビッド・リンチの「ブルーベルベット」中でディーン・ストックウエルが、ロイ・オービソンの「イン・ドリーム」をカラオケで歌うシーンがある。
「アキラ2」のCDを部屋で聞いているとまさに気分は「ブルーベルベット」。
「アイズ・ワイド・シャット」を撮りたくなったキューブリックの気持ちがよく解る。若くして既に「懐かしさ」を歌う事の出来た旭だが、このムードを醸しだす最大の原因はなんと言っても水島哲の超絶的歌詞によるところ大である。
「理性的にみると何を言ってるのかさっぱりわからない」から郷愁を誘うのだ。
学問の対極にある様な歌詞は、「何故」という学問の原点を真っ向から受け付けぬどころか、歴史の体系の外で歌詞として成立し存在し、人に歌われ、残る。
頭で考え、言葉で論じる事の空しさを思いっきり思い知らされる水島哲の詞はいくらでも書けるか、一編も書けぬかという恐ろしいものである。
世の中に2種類の人間がいるとすれば、このどちらかに分類されると言っても過言ではないが、どちらもそれを意識的にやればたいてい野暮になり、無意識なら
単なる戯れ事に終わるというたぐいだ。すなわち作詞家としてきわものスレスレを行き見事に昇華にまでもってゆく手腕が問われる詩人の
冒険として最も魅力的なチャレンジである。
そしてそれは「芸術作品」という顔をしていてはならない。私事だがこれは私の一番好きなアイテムであり状態だ。
桑田佳祐の詞もこの流れにあるんだろうが、意識的すぎて嫌味なものが多い。
「落日のシャイアン」題からしてポエムだ。書き初めの御題にしてもいい。
多くはそのまま原詩を日本語訳したような「乗り」で書かれているが「南を指して飛ぶ渡り鳥とともに南に旅行く(俺)が振り返って見上げる夕月は北に霞んでいなければならない」し、
「落日の他国は西だが、そちらを振り返ったのなら行く先は東だ」。
日本人よりよほどロジカルな外人がこのような方向感覚を無視したような詞を作るとは思えない。
「アキラのボサノバ」の2番にある昼間なのか夜なのか時間を無視したような歌詞といい、これはすべて天才水島の創作だと思いたい。
殆どの歌詞に多用する「あの娘・あの時・あの日・あの空・この胸・この街角・
あの渡り鳥・あの星・このギター」が時間空間を超越した作詞家を物語る。
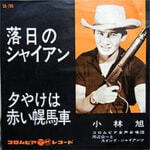
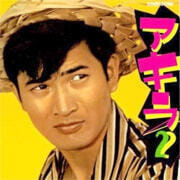
親愛(戦友)なる函館ヒトシさんへ「夢ん中」
2003/01/10
「一体これでいいんだろうか?」生きていれば人間誰でも常に自問自答の連続だ。しかし事すべて「夢中」になっている時には、こんな疑問は出てこないのも人間。「夢中」になることの大切さ、そして「醒める」ことの重要さ、言い換えれば、「罪」を犯すことの大切さ、そして「懺悔」の重要さだ。
男のつらさと女のつらさは多分違う、だけど「男と女」のつらさは極めて
人間的なつらさに間違いない。色香に迷ってこそ男だし、寂しさに耐えきれないからこそ女である。踏み外し、落ちて、迷って、後悔してこそ人間なのだ。
「それでいいのさ いいんだよ」というフレーズは、この道程を経てはじめて出てこなければならない、人間という生き物への解答だ。般若心経といってもいい。
このセリフを言える者は、この世には存在していない。人間以外の誰かでなければならないというのが、この種の宗教的な説得の辛い所だが、さすが阿久悠のやり方は上手なもので、人間世界をすべて「夢ん中」にすることで矛盾を回避しようとしている。
このフレーズは「夢ん外」にいる「俺」が言っているのだ。しかしこの「俺」だってだれでもなれるものではない、この「俺」の役を務められる人間は旭しかないだろう。
そこらへんの社長さんが「それでいいのさ いいんだよ」といったら要注意だ。その後に続くセリフは決まって「うちは、慈善事業をやってるんじゃない」だ。
「なんでもありを」正当化したらもうお終いなんである。しかし、こういう事を歌詞に盛り込むと、とかく教条的になってしまうので、阿久悠はちょっと工夫を凝らしている。ぜひ検証して頂きたい。印象的でうまい形容詞に
気を取られていると、見落とすよ。
1番2番はそれぞれ4つのかたまりでできているが、各番の1つめのかたまりは実は、あべこべになっている、入れ替えた上でさらに1、2番をもういちど入れ替えたものが、はじめの歌詞だったと思われる。シャッフルしちゃったのだ。
何故こんなことをしたかという理由は、簡単である。
「本当のことというのは、それが本当のことであればあるほど嘘っぽい」と
言うことを、この作詞家は知っているからだ。要するに照れ隠しなんである。
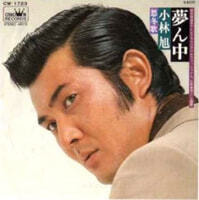
秘すれば花「熱き心に」
2003/01/13
旭の歌の中でも、現在最も幅広い層から支持され浸透している曲といえば、この歌をおいて他にない。旭には素晴らしい曲が他にもてんこ盛りだと声を大にして叫びたいが、ヒットソングとはそういうものなんだろう。それで生きられるのだからヒットソング様々というところだが、他の曲が、影に隠れてしまうのは残念である。
何事も、表面で目立つものと、水面下で、目には触れぬものとで構成されている。目に見える物だけが全てではないことは、あらためて言うまでもない真理であろう。
さて、「作詞界の業師」阿久悠である、この歌詞に主に意図したものは何だろう?
まず誰もが注目する春夏秋冬だが、それぞれに割り振ったフレーズは視覚的に、きっちり計算されている。1番は「地上に咲く花と天上に輝く星」の空間的対比。
2番は「色づく(葉)と真白な(雪)」のフルカラーとモノクロの色彩的対比がそれで、どれも極めてヴィジュアルな性格を持ついわゆる物理的な個体である。
ここまではソングを離れ歌詞を見れば気がつくであろう、しかし一般的にサビといわれるこの部分に作詞家の意図があるのではない。むしろサビ以外の部分を浮かび上がらせるための手段としてこのパートを構築したと考えられる。
すなわちヴィジュアルとは反対に「目に見えないもの達」こそこの歌の主人公。
つまり「別れた女(ひと)」であり「なつかしい想い」であり「夢」であり「愛」であり「歌」であり、「熱き心」なのである。そしてそれら総体としての「時」。
目に見えるものも、もちろん感動的だが、目に見えないものはそれ以上に、
胸に訴えてくるんだよ、というのがこの歌のコンセプトだと言えよう。
旅人である旭ですら「風の姿に似て」この詞の中では見えないもの達の一部だ。
さて、まえにも述べたようにこの作詞家照れ屋なんである、哲学者を気取って「見えるもの」と「見えないもの」をテーマに歌詞を書きましたと言わんばかりの作品を好まないので、この両者のコントラストをわざとぼかすためにその中間的存在を2つばかり、すなわち「気体」「光?」を放り込んである。
目には見えるが、物体として存在しない「雲」と「オーロラ」である。
こうして、歴史的ヒットソングは生まれたのであった。
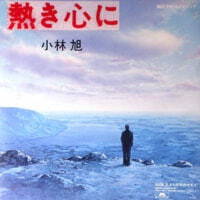
追悼深作欣二「やくざの詩」
2003/01/14
わずかでも伴奏があるのだからアカペラとはいわないのだろうが素の旭の声を、伴奏に邪魔されずクリアに味わえる曲である、ナマの迫力。しかも若い。
タレント風に崩し、書き慣れたサインでなく、旭から楷書のサインをもらった感じだ。いっそ全曲この吹き込みで聞きたい。
「仁義無き戦い」という映画は、俳優がみんなこの「楷書」でやっていたような気がする。もちろん旭もだ(彼にとってはだからあまり気が進まなかったんだろう)。
30年以上の記憶をたどれば、その他桜木健一や渚ゆう子、小倉一郎などの演技にひかれるものがあった。肝心の菅原文太さん、北大路さんあたりが「楷書」ではなかったけれど。「記号」としてのやくざではリアリティーに行き詰まり「楷書」でやったらうまくいった、みなさんというより日本人の地、素の姿がやくざそのものなんである。しかしこれが許されるのは1シリーズ限りである。
真の失恋が一度だけであるように。私には「バトルロワイヤル」の“2”を作る監督の意図がわからない。生きていて完成後にお聞きしたかった。見たかった。
バトルは若い人に任せ「殺し合いよりイカシた愛」の映画がまた見たかった。金子さん、川谷さんはじめ沢山のひとの逢えますね、さようなら。
やくざの詩…ということだが、この歌の歌詞から「やくざ」の3文字を取り去ると、一体どこがやくざの詩なのか全く解らなくなる。その形跡すらない、ごく普通の失恋の歌なのである。わざわざ「やくざの詩」という題をつけるのが、ちょっとためらわれるほどの単なるロストラブソング、傷心の歌そのものではないか。
しかしそんな失恋なら山ほどあるだろう、この失恋が真の失恋であるためには恋自体が2度と帰らぬような恋愛でなければならない。すなわち引き返せない道。
とりかえしのきかない恋の詞にするために必要な「やくざ」の3文字、この3文字でこの失恋歌が独自の「詩」を放つ。これは求め合っていても決して叶わぬ恋かもしれない。
ヤクザ人生にやり直しがきくなら、気質(かたぎ)人生の再出発より数倍漫画である。
私には転んでも歩めぬ真剣勝負の道だが、自分の中に強い憧れがあるのも否定出来ない。