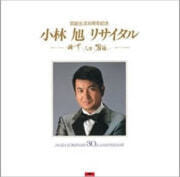「ズンドコ節」
2002/12/21
この歌を、日本の「国歌」にしたい。
アタマおかしいんじゃないの?と思った人、反省して貰います。
「だってこんな高い声出ないし、歌えないよ」
じゃあ、君が代歌ったことあります?
君が代が悪い歌だとは思わないが、歌わないんじゃ国歌といわれても。キーを少し下げれば1オクターブプラスしかない。子どもの頃から慣れていれば歌える、ポジティブで前向き、優しさあふれる曲を味わおう。
掛声の「ズンドコ」がいい、ずんずん何処までもだ。
これでみんなが一緒になれるし、人種年齢を問わず一度聞けば忘れない。
そしてなによりこんな素晴らしいラブソングは滅多にない。
ラブソングのない国は存在しない、恋を否定出来る人間もいない。
言葉が解らない外国にも「アイ・ラヴ・ユー」と、誰も知ってる国際語が入っているのもいい、メッセージと受け取ってくれるはずだ。
歌詞全24行中、20行は、もう抱きしめたいほど素敵だ。
中でも「グットナイトと二人に ウインクしている街あかり」
このフレーズの可愛らしさ、これが「グッドナイト」ではぶち壊しだ、ぐっと来ないでしょう。「ふりかえる・もういちど・ただひとり」のリフレインは歌えるようになると実に気分がいい、優しい気持ちになれる。
フレーズの魅力は語り出すときりがない。
さて気になる残りの4行だが、この4行がなかったら国歌には推薦しない。
「一年前には知らなんだ・半年前にも知らなんだ・若い二人がいつの間に・こんなになるとは知らなんだ」の4行、他の20行とは視点が別だ。
「僕」人称ではない。では歌っているのは一体誰だ。
「星でしょ」「正解!」、でもいいが、ここはやはり少しミステリアスに二人の成り行きを高い所で見ている「だれか」とするのがいい。誰も振り返らなくたって、この「だれか」が二人の恋の世界の外で見ているという視点がここにあるからこそ高い完成度。
ラブソングにありがちな独りよがりがこれで救われ、みっともなくない。
昔「世界は二人のために」とかいう歌があったがこういう自己中心的な曲が受け出してから、どうもおかしい。
「だけど星が降るって、場面は夜、星はヨーロッパとか米国・中国・ロシアのイメージだよ」
「星にも夜にも国境はない、それより歌手の名前をよく見てください
「旭」と書いてある、これが我が日本のシンボルでなくてなんなんだ」
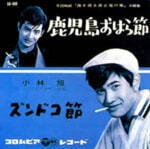
「やどかりの歌」でござんす。
2002/12/23
股旅ものと言えば、旅ガラスということになろうが
鳥のカラスというイメージは、旭には遠い。
やはり鳥ならカモメ、海燕だが、時代物それも三度笠となるとこの鳥たちはモダンなところもあるのでカリカチュアには少し無理がある、「てなもんや」なコスプレになってしまってはまずい。
擬人化するにあたって、鳥ではないがヤドカリとはよく考えたものだ。小さな感じもいいし、その姿かたちには滑稽にまで堕ちない愛らしさ、愛嬌がある。渡世人に愛らしさ、愛嬌?、そうこれは重要なポイントだ。
あまりニヒルに傾きすぎるのは、旭の魅力をスポイルさせるからだ。
旭になり代わって小石だらけの寂しい磯を動くヤドカリの姿は、実にリアリティがあるではないか。擬人法はこうでなくてはいけない。
さて借りたのは宿だけか?、どうもこの歌、相当凝っている。
ヤドカリに姿を借りて歌われる歌詞だが、まず「情ヶ島」「城ヶ島」を音で踏み替えている、歌詞を見なければわからない。
歌は耳で聞くものだから、音として歌詞は入ってくる、それを計算して、ダブルミーニング効果を作っているのだ。つまり「小石→恋し」「重い→思い」「たびに→旅に」「いわば→岩場」が、そのようにも聞こえる事でイメージが往き来し風情を盛り上げる。
さらに、小さな甲羅(殻?)の宿と、大きな海という宿の相似形。
この世は大小の差こそあれ有限であり、相対的なものの間を転がって
まるくならざるを得ないのか、ということを歌詞に姿を借り余すことなく盛り込んで歌詞の構造にまったく破綻がない。
しみじみとした旭の声と相まって物語・寓話としても、またおとぎ話としても素晴らしい作品である。
付け加えるならこの歌も「ら行」が多い先に「さすらい」「思い出酔っぱらい」を挙げたがこの曲、題はもちろんのこと、全編に「ら行」が散らばった旭ボイスのためのパーフェクトソングだった。
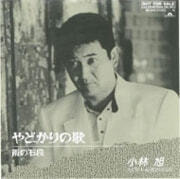
「巷の子守歌」
2002/12/24
新しいCDなどを買った時はついジャケットを見ながら、そしてライナーノートなどを読みながら、曲に耳を傾ける人は多いと思う。
そこまではいいとしても、歌詞を目で追いながら聴くと文や言葉をロジカルに受け取ろうとする力が働き、心ではなく頭で聞いてしまい歌そのものの真の味わいが、ともするとスポイルされるのような気がして、初めて聞く時は(見たいけれども)歌詞カードは見ないように、というのが、私の聴き方だ。言葉よりやや音を優先して聞くわけだ。
そして想像であれ歌詞体験を共有するためにともかく声を出して歌う。自分で歌ってみて初めてその曲の味わいに気付くことがある事を、たとえ歌うのが苦手な人も、聞くに徹する人も知っておくべきである。
更に、歌いつつ節回しが自分のものになった時初めて曲に血が通い歌の真髄が見えてくる、ということも…。
ここまでくれば、「いい曲だよね」で十分、もう歌語りなど無用の長物「言うも恥ずかし」なんである。けれども、ここからわざわざ理屈をこね何故語るかといえば、旭を先入観や表面だけで捉えている連中(なかんずく自分も含め)にパンチを食らわせたいからだ。
さて私に長い前置きを書かせたものこそ「巷の子守歌」である。
「子守歌」は、当たり前だが歌詞カードがない、聞く方は原則的に言葉の意味さえ解らぬ赤ん坊である、にもかかわらず確実に何かが伝達されているというこの不思議。しかも「子守歌」は作ろうとして企てたものではない、なかば自然発生、口伝えであって、「作品」ではないのだ。こんな形而上領域に挑むというのは、作詞家として意気に感ずれどこれを踏まえた上でなければなまじ子守歌など書こうと思わぬ方がいい。
全編ぽっと浮かんだそれらしいシンプルで数少ない言葉を並べただけのように見えるがこれが全くの思い違い、実によく練り上げられた内容と歌詞構造を持っている。この美しくやさしい歌のインパクトはたしか、昔いつだったかどこかで出会ったことのある感触、そうこの曲はいってみればオスカーワイルドの「幸福の王子」だ。
このハイカラーさ!、詩人としての志の崇高さ、人としての教養の深さ!
ツバメが王子の願いに従って、村の様々な貧しい家ごとに、王子像の装飾として使われている宝石や金箔を剥がし、届けるという童話をご存じの方も多いだろう。
目である宝石を持って行かせ盲目となった王子は、貧しい村の家々の様子を、ツバメに代わりに見に行かせ、見てきたことを話して聞かせてくれと言う。歌詞構造は1番から4番までそれぞれ独立していて、例えば巷のどこにでもあるありふれた人生や生活の姿を、ちょうどあたかもツバメが一軒々々覗いてまわり、時に個人を、時に民衆の姿を赤裸々に私たちに話してくれるように作られている。
そしてそれら個々の窮乏と悲しみに、さしのべられる心が秀逸だ、
すなわち
1番、故郷(基盤)の喪失、過去への郷愁には「なぐさめ」を
2番 物質的貧困には「励まし」を
3番 精神的欠乏には「優しさ」を
4番 羅針盤故障、漂流、未来への不安には「共感」を注いでいるのだ。
あたかも幸福な王子が1枚1枚、身を削って与えるように。
1~3番は、同じ一人の人間の複数の断面と考えても良いが独立した個々の人だと考えたほうが「巷の--」を反映している。私もこの中のどれかに違いない、万一このどの軒にも属さないと言う人がいても、このツバメはあなたを見逃さない。
「1軒、2軒、3軒」、それから「残り全軒」という4番の歌詞には唸らざるを得ない。この王子は、個々人はもちろん、必ずあなたを含む全体をも救おうと思っている。
子守歌は子供にとっては歌ってもらうもの、大人は子供に歌ってあげるものだが、このツバメ(旭)は、お前自らが自分の持っている物をすべて投げ出せるような
「幸福の王子」になれよと、言葉を越えた歌声(子守歌)で言っているようだ。おしまいには一緒に死ぬ石像の王子と鳥のツバメとのあいだに交わされた心と心は、そんな種類のメディアで、通じ合っていたに違いない。

じゃあ行きますか「十字路」
2002/12/28
ずばり「あきら(め)」で始まるこの歌、詞は西沢爽、曲は遠藤実心して聴くべし、歌うべし。名曲である。
十字路は二つの道がぶつかる交点、人で言えば2人の人生の出会いの場、と同時にそこを境に再び離れてゆく運命的なドラマチックスポットである。やって来た一方の道に追随するなら、これはハッピーと言うんだろうが「会うが別れの初めなり」が旭のセオリー。もっとも追随したって人生やがて死が2人を分かつのだ。
ふかい霧の十字路に一つ灯るすみれ色の明かりは、街路灯かそれとも二人のはかない夢か、清楚で可憐なすみれ色が二人の純愛を象徴し、「交差点」と「くちづけ」の絶妙なバランス。
「落ちる枯葉」と「もう逢えないさよなら」は、ばかに相性が良すぎるが落ち葉はすみれと相対しこの十字路を人工的なバーチャル空間にさせないための重要なファクターだ。そして「霧」は「切り」も暗示する。
「愛しいあの顔が 消えてゆく」なんと素晴らしいフレーズ、ほかの歌詞はこのフレーズのための舞台設定である、これ以上のロケーションは少ない。気付いた方もあろう、「あの子」でも「あの娘」でもなく「あの顔」である。
旭は「「あのこ」と歌っているので歌詞を見なければわからない。
いくつかの歌詞をあたってみると、例によって大滝さんの歌詞カードが
「あの娘」になっているが、これは明らかにミスプリである。1番が「くちづけ」2番「ふりむく・うなづく」3番「涙・唇・噛みしめ」と、徹底的に顔面にこだわっているからだ。
勿論、歌う時は「あの娘」と歌って、後ろ姿を想像してもかまわないのだが、なんとも寂しい情景の中で「そっとうなづく」表情と仕草をいとおしむ別れの切なさを、「人間の持つ顔の表情に集中」させた方がぬくもりと未練が冴えるではないか。
もし純粋な恋愛というものがあるなら、それはまさに十字路での激しい出会いと、悲しい別れになるはずだ、鈍角で交わるのではなく並列でもなく、直角で交叉する男と女。この歌は今後何年たとうが色あせることはない。
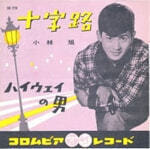
「ギターを持った渡り鳥」
2002/12/29
「終わりよければ すべてよし」「赤い夕陽」で始まり、同じ「赤い夕陽」で終わる1番のみならず「汐の匂い」「別れ波止場」と2、3番とも初めと終わりは同じ語句である。この構成にまず50点。
童謡を思わせる平易な言葉だけで作られたこの歌、美しいメロディに乗せられていると、あまりにも自然に先頭と末尾が接続するので、歌詞を見るまで全く気が付かぬほどだ。難解表現のないことに10点。「童謡」と侮る無かれ、西條八十も北原白秋も童謡こそ光っている。
この後沢山の唱歌や童謡を歌う旭になんの違和感があろう。
無駄をすべてそぎ落としたような歌詞の中に、「燃える落ちる夕陽とそれを冷却する海の温度差」と「熱い胸の涙とそれを乾かす風の冷たさの温度差」という「ホット&クール」をさりげなく折り込むテクニックに10点。
若いということの、黄金のような価値を思い知らされる年になると「俺も あの娘も 若いから」のフレーズの輝きはたとえようもない。
ともするとなんともオメデタイ表現に堕するこのフレーズも「夢よさよなら 渡り鳥」のあとにこれが来ることで陳腐にならずそれどころか年齢を問わず歌える曲になっているのだ。10点
そしてその生命感を歌詞全体にちりばめた生理感覚は、五感で言えば
視覚「赤い夕陽」・嗅覚「汐の匂い」・聴覚「つま弾けば」
・触覚「指にからむよ」とまことに豊富で、珍しく嗅覚も含んでいる。
こんなガチガチの分析が可能にもかかわらず、歌えばこれ以上の旭ソングもないというほど、この歌は「小林旭」そのものだ
この歌詞をタイムカプセルに入れて100年後に未来人に見せ、歌手をたずねてみるがいい、即座に「旭」と言うに決まっている。
さて、この歌詞に味覚表現はないが、旭の声でこの曲を堪能する喜び
これ以上の「味覚」はあるまい。当然20点で満点になるだろう。
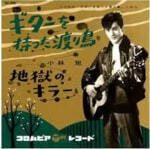
「雨の石段」
2003/1/1
男たるもの、もう一方の性に対しどういう距離を保つかというのは、文学のみならず絵画の世界でも永遠のテーマだ。歌だって同じ。
「思わず触りたくなるような」でも「安易に触るのがためらわれる」ような価値ある女が少なくなったなあ。女性だけじゃあなくて今はそういうものがあまりになさすぎる。
「簡単に触れるけど、触りたくない」ものばかりだね。
さあ旭になって女性を見つめてみよう。
人が見る対象物には3つのタイプがあると思う
一つは「動いているもの」二つ目は「静止しているもの」そしてもう一つは、矛盾するかもしれないが目ではなく心の目で見る「思い出あるいは幻想」である。この3タイプを美しく歌詞にこめた「雨の石段」は、女性というものに対して独自の視線と捉え方をする「お世話になったあの人へ」の作詞家はフェミニスト中山大三郎である。
深刻に構えず、明るい曲調も好ましい。
1番は「動」。和服に蛇の目傘とともに石段を下る動きある華麗な姿は女性の持つ生命力ある輝きをもって目の前に迫ってくる。
「階段を降りる女性」でそれまでの絵画にインパクトを与えたのはマルセル・デュシャンだ。
3番は「静」。障子の格子のように折り目正しく「形」を決めた女性には近寄りがたい気品と色香りが漂い、息をのむ。
旭が歌う女にはこのタイプが多い、汚れていても、貧しくとも気丈さがあってひたむきで、下品に意気込む様なこともない。
そして2番は「まぼろし」。これを2番にもってくる所がニクイ。
「遠い過去になってしまうと、夢で遊んだ女と、実際に接した女の区別がつかなくなる」と吉行淳之介がどこかで言っていた。
所有とか一体感とか言うけれど、ただ燃え上がるだけでなくこんなクールなスタンスと想像力を保つスタイルがあることを旭が改めて教えてくれる。